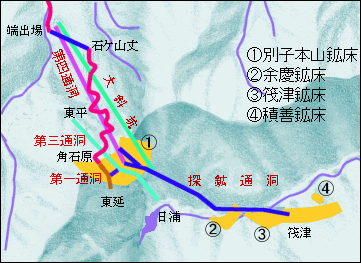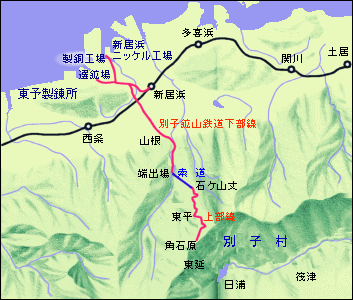
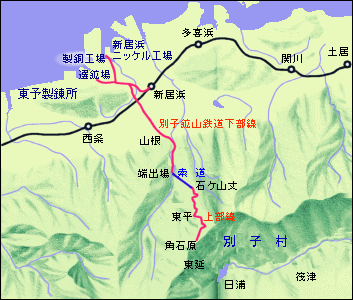
愛媛県にある別子鉱山は、元禄3年(1690年)の開坑以来、283年の永きにわたって稼行し続けた日本を代表する大銅山である。この間に産出した銅量は、約65万トン。江戸時代の貿易経済を支え、明治以降のわが国の発展にも大きく寄与した。
別子鉱山は、開坑から閉山まで、常に住友家と関わり続けてきた。その屋台骨を支え、時には住友そのものだったといっても過言ではない。平成3年、住友金属鉱山㈱は、別子開坑300年記念事業の一環として、鉱山の歴史を後世に伝えることを理念に、「住友別子鉱山史」を編纂した。言うなれば、正史である。その中で当時の社長篠崎氏は、別子の偉大さを振り返る一方、こう語っている。
「歴史は決して、平坦なものではなかった。数々のロマンもあったが、それをはるかに上回る艱難を克服した先人の苦闘の歴史でもある。
別子を襲った天災や重大な経営危機は、旧別子山中の蘭塔場に犠牲者の墓碑を残す元禄7年の大火、幕末・明治維新時の新政府による接収の危機、死者五百余名を出した明治32年の大水害、約半世紀にわたる新居浜・四阪島製錬所の煙害問題など枚挙にいとまがない。
しかし、我々の先人は英知と勇気、果敢な行動力をもって危機を乗り越え、難問題を解決し、別子鉱山の経営をますます盛大にするとともに、これによって住友事業発展の基礎を築き上げた。」
別子鉱山は、住友にとって、今でも企業精神の土壌であり、心の故郷となっているのだと思える。
別子が閉山して、はや30年近い歳月が流れた。日本の鉱山全盛時代はすでに去った。鉱夫たちの痛ましい苦労や、生々しい鉱害問題は、多くの人にとってもはや親身に感じ取れない出来事となった。
しかし一方で(未知の)「鉱山」に対する懐旧とロマンの念は、新しい世代の鉱物愛好家の胸を、今になって、より激しく揺り動かしているのではないだろうか。
このページでは、かつての別子鉱山の様子を彷彿させる資料をいくつか提供する。一つ一つの資料には、何も味付けをしていないが、時間のある時にでも、ゆっくりと辿っていただけるなら、文字と文字の合間から、往時の香りが立ち上ってきはしないだろうか。筆者自身は、ページを作りながら、しばし山の底深くに広がる巨大な鉱洞に遊ぶ心地がした。端出場から大斜坑を走り抜けて本山鉱床へ赴けば、そこは海抜-1000mのレベル32である。海水面よりやや高い、目抜き通りの第四通洞はレベル14にあり、そこからさらに6キロ近い水平トンネルを行けば、筏津の第一下部斜坑に達する。含銅硫化鉄鉱の鉱柱がキラキラと闇の中に瞬いている…。それは、あるいは局外者の視点から見た、無責任な憧憬かもしれない。しかし、私たちはこのようにして、見知らぬ王国である鉱山の世界に一歩ずつ近づいていくのである。
その胸に、感興が満ちますように。
資料の多くは、上記「住友別子鉱山史」(3巻本)に負った。機会を下さった方々に感謝を。
SPS