|
|
| 注:西域都護府は匈奴を駆逐するための軍隊駐留府で、BC60年に設置された。 |
このページでは、前漢の武帝の時代に、どういう経緯でホータン玉が中国にもたらされたかを、もう少し詳しく辿ってみることにします。
次の地図をご覧下さい。前漢当時の中国大陸の勢力図です。濃い茶色の部分が武帝以後の漢の支配圏です。 北方の匈奴に対する守りとして、万里の長城が蜿蜒と伸びているのが分かります。匈奴は、BC4世紀頃、西方から現れた騎馬民族で、戦国時代の終わりからしばしば華中に侵入していました。 長城の西端は敦煌のあたりまできていますが、 これは西域への領土拡大を受けて武帝の時代に延長されたもので、秦の始皇帝の頃には、横に並んだ3本の城壁のうち、 右から2本分まで(及び2本目の東端あたりから南西へ伸びる城壁)が築かれていました。 逆にいうと、このあたりまでが秦の領土だったのです(下の世界地図を参照)。 そこから西は、河西回廊を経て、北を天山山脈、南を南山(崑崙山脈)にはさまれたタクラマカン砂漠が広がり、 広大な土地に西域36カ国(36は多数の意味で、実数は50有余という)と称されるオアシス都市国家が点在していました。 彼らは武帝の時代まで匈奴に朝貢しており、西域は匈奴が自由気ままに跋扈する土地となっていました。なみに、ウイグル語で「タッキリ・マカン」は、生きて還れない広大な土地の意味。日本がすっぽり入るこの砂漠をよく表しています。
|
|
| 注:西域都護府は匈奴を駆逐するための軍隊駐留府で、BC60年に設置された。 |
武帝以前、代々の皇帝は匈奴に対してひたすら辞を低くして貢物を贈り、どんな無理難題にも、ご無理ごもっとも策をとってきました。漢は匈奴に侮られながらも、戦を起こさず、次第に力を蓄えていたのです。そして、青年武帝が帝位につく頃には、一大合戦を起こせるほどの金と力を備えるようになっていました。
武帝がまず考えたのは、遠くの国と仲良くして近くの敵を攻める、という先達の兵法でした。その頃西域にあった月氏国が、匈奴に追われてさらに西方へ逃亡を余儀なくされ、匈奴を恨んでいると聞いた武帝は、まず月氏に使者を送って和を結び、双方にとっての敵、匈奴を挟撃しようと謀りました。しかし、使者を送るといっても、月氏国までの道程はまったく未知の世界であり、匈奴の領土を通過する以外に辿りつく方法もありませんでした。当時、漢と匈奴は一時的な和親状態にあったとはいえ、あまりに危険な任務です。その使者に立ったのが、一介の小役人だった張騫でした。
張騫は、後に「生まれつき堅忍の志と寛大な心を持ち、よく人を信じ異民族に愛された」といわれた人物です。
西方に出発後、案の定、匈奴の土地を通過している間に捕えられて、10年間の足止めを喰らいますが、機を見て逃げ出し、任務を続行しました。砂漠を横断して、大宛(フェルガーナ)に辿りつき、そこで漢の使者として厚い歓待を受けた後、隣国の康居国に送られ、さらにその南に移っていた大月氏国へと送られました。こうして長安を出発して11年、ようやく目的地に辿りついたのです。ところが、月氏は新しい土地で豊かな暮らしを楽しんでおり、もはや匈奴を討とうという気持ちを失っていました。張騫は、さらに月氏が臣従している大夏国や西方の安息国に赴いて、武帝の意を伝えますが、やはり同盟には関心がないという返事です。
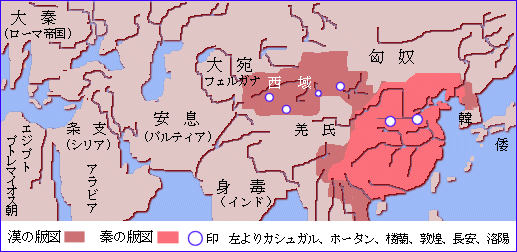
|
こうして任務は果たせなかったものの、張騫は行く先々の国で丁重に扱われ、ともかくも漢の使者としての面目を保ちながら、再び長安に帰ってきました。ときにBC126年、出発以来、13年が過ぎていました。
この間、漢と匈奴の関係にも変化がありました。帰国の前年、若き将軍、衛青の軍隊が匈奴を打ち破り、実に87年ぶりにオルドスの地が中国に戻っていました。漢は、すでに単独で匈奴を攻める態勢が整っており、もはや月氏との同盟に執着する理由もなくなっていました。武帝はむしろ、張騫が旅の途中に見聞した西域の情報を高く評価しました。西方諸国の産業や物産、政情に関する情報が華中に知れたのはこれが初めてであり、今や西域に対する熱い関心が呼びおこされたのです。たとえば、草原を駆け血の汗を流すという大宛の汗血馬の話は、武帝の憧れを掻き立て、西域への進出を決心させる端緒となりましたし、同じく大宛で見たという、中国特産の絹織物は、商人レベルで、蜀からインド(身毒)を通じ西方の国々と東西交流があったことを明らかにしました(漢から貢納された絹を、匈奴が安息国に売っていた経緯もある)。張騫の報告をもとに、武帝は西域経営に乗り出し、やがて地図に示すような広大な領土が漢の勢力下に入ることとなるのです。
張騫の西域行は数々の予期しない収穫をもたらしましたが、その白眉は、黄河の源流に辿りついたこと、源流地域で玉の大産地を発見したことでした。大黄河は、中国人にとって母なる河で、その源を知ることは歴代皇帝たちの果たせぬ夢だったのです。それがついに見つかったというのですから、
アレが見つかった!
何が?
永遠がさ!
というくらいの壮挙でした。
黄河の源は、土地の人々がただ南山と呼んでいた(南にあったから)山脈の奥深くにありました。そこから流れ出た水は、北流して山を下り谷を走り、タクラマカン砂漠のオアシス都市ホータンを通って東西に分かれます。東に向かった流れは楼蘭にある湖ロプ・ノールに注ぎます。そこから伏流して砂漠を抜け、積石で再び地表に現れ、黄河となって海に向かうというのが張騫の報告でした。(この説は、地理学的には正しくないらしい)
積石は、今の青海または甘粛あたりの地名で、冷静に考えると黄河はそこで途切れているのですが、大いなる河の源がそんなに近いところにあるはずないというわけで、地下水脈をさらに遡って源流をはるか西方に求めたのでしょう。彼の報告は、武帝を大いに喜ばせました。なおさらに素晴らしいことは、その山の中から、玉が大量に出たということでした。玉は、川を下って麓に流れ出すので、ホータンの城外でも沢山採ることが出来、張騫はそれを持って帰ってきたのです。
玉は中国人の心に染み込んだ大切な宝物で、古くから人界と霊界を媒介する奇しき霊力を持った存在とされていました。そんな玉が、彼らの心の故郷、黄河源流にあったというのですから、まさに不思議な暗合でした。感激した武帝は、古い書物をあれこれと引っぱりだして、河の源である山の名前を考え、ついに「崑崙」と名づけることまでしました(「史記・大宛伝」など)。崑崙とは、伝説の仙女、西王母が住むとされた桃源郷のことです。その昔、周の穆王(BC10世紀頃)が西の方に赴き、西王母にまみえて、不老長寿の霊薬を授かったという伝説は、仙人に憧れた武帝の心を捉えて離しませんでした。そして不老不死の生命力を持つとされる霊玉の産地が黄河の源と同じだったことがわかった今、この山こそ、西王母の住む伝説の「崑崙の丘」であろうと決めたのは、まことにもっともなことといえましょう。
武帝がどんな書を参考にしたのか定かではありませんが、試みにそれらしいお話を拾ってみますと、
BC6世紀、春秋の晋の平公が、船に乗って水の流れを見ながら、「どうしたら賢い人を見つけ出し、共に政治を語り合うことができるだろうか」と嘆じた。それを聞いていた船人の固桑は、「呉王夫差の剣は越に出ました。真珠は江漢に、玉は崑崙に出ます。賢人も同じように、かならず自ら現れることでしょう。」と答えた。(「新序」)
BC4世紀、涼の第四代文公が死んだとき、世継ぎの重華が、青海は酒泉(地図中、敦煌と武威の中間にある土地)の領主馬笈に葬儀を諮ったところ、「酒泉の南にある山は崑崙の体をなしています。むかし周の穆王が西王母に会ったのはこの山です。山中には石室玉堂があって、珠璣などの珍宝が納められています。神官の手で王母の祠を建てて祀れば、国は大きく広がるでしょうと申し上げると、父君はその通りなさいましたよ。」と答えたという。(「晋書」列伝)
こうしてみると、ホータンの南の山が崑崙と名づけられる以前に、玉の産地として崑崙と呼ばれる土地があったこと、酒泉の南のチーリエン山脈が、昔は西王母伝説の桃源郷とみなされていたことが覗えます。突っ込まれると困りますが、たまたま武帝がホータンで玉の採れることを知らなかっただけで、世間では周知の事実だったのか、それとも別に崑崙という玉の産地があったのかよくわかりません。西王母が住むといわれる場所は、タクラマカン砂漠の北の天山山脈にもあって、天池と呼ばれています(山の上に池がある)。そもそも伝説の土地ですから、いくつあったって構わないので、山海経には崑崙と呼ばれる別々の山がたくさん載っている、と伊藤清司氏は言っておられます(「死者の棲む楽園」)。玉はホータンにしか出ないと言われていますが、昔知られていた産地が忘れられたということもありえるでしょう。だから、まあ、あんまり気にしないことにしましょう。ともあれ、こうしてホータンの玉は見出されました。(現在酒泉で採れる酒泉玉(老山玉)は、蛇紋石の一種にあたり、ホータン玉とは別種です。)
その後の西域開発の流れを簡単に記しておきます。武帝の軍は、BC119年ついに匈奴の主力部隊を殲滅し、西域へのパスポート、河西回廊を手に入れます。本格的な西域遠征が始まり、BC115年、張騫は、中郎将の官位をもって烏孫国(当時の西域では群を抜く大国だった)へ使者として旅立ち、良馬数十頭を献じられて帰国しました。この時一緒に連れられてきた烏孫の答礼使節は、漢の都の威勢に驚いて、烏孫王に同盟を進言したので、両者はめでたく手を結ぶこととなりました。その翌年、張騫死去。
BC108年、西域に向けて最初の武力発動。楼蘭を攻略。酒泉で止まっていた長城は、領土の拡大につれて、敦煌の西85キロの玉門関まで伸ばされました。交通路が開かれ、諸国の使者が頻々と長安に来朝するようになります。西域の珍しい産物が相次いで都にもたらされました。火吹き男や手品師なんかも朝見したようです。
BC102年、汗血馬を求めて2度目の大宛遠征。大宛の和睦を受け入れて、念願の天馬を得ます。この勝利は西域における漢の威信を決定的に高めました。西域諸国は王族を使者に立て、競って朝貢に上りました。また、この勝利を境に、東西通商路の安全が確保され、シルクロード交易が俄然盛んになりました。かつてアレキサンダー大王のインド遠征で整備された西方の道に、漢までの東方の道が加わり、大陸を横断する長い長い道となって東西の思想や文化をシルクロード上に往来させました。
漢の勢威が確立すると、ホータン国は進んで土地の産物を朝貢するようになり、大量の玉が武帝のもとに集められました。これまで華中で採取されていた玉と違って、ホータン玉は皇帝の独占物となり、皇帝から各地の王侯へ、また功績のあった臣下への贈り物となりました。玉の独占を維持するため、玉門関では玉の密輸が厳重に監視されました。
宮殿の宝物庫は何十万枚という玉でたちまちあふれかえりました。一部の玉は、宮廷出入り商人の手で、民間にも流され、非常な高値で取引きされました。ホータン玉ブームが起こり、玉文化に新しい流れが生まれました。漢の時代には、皇帝や皇族は、玉衣をつけて埋葬されるのが習慣となりました。武帝の庶兄、中山王劉勝夫妻は、金糸、銀糸で綴られた約2500枚の玉札で作った葬衣に包まれて埋葬されましたが、その墳墓からは玉豚、玉璧、玉枕、玉亀、含蝉を始め、大量の玉製品が出土しています。
含蝉は蝉を象った玉で、口に含ませて埋葬すると遺体が腐らないと信じられ、皇族に限らず、富裕な民間人の間でも葬儀に用いられました。なんで蝉なのか、という気もしますが、蝉は幼虫が木に登って羽化をする、そのように魂が羽化して昇天することの、あるいは肉体が再生することの象徴だったのでしょう。手には豚をかたどった小さな玉を握らせました。豚は豊かな財産を意味し、あの世でも安楽に暮らせるようにとの配慮です。
金鏤玉衣は、写真で見るかぎり羊脂白玉ではないようです。ホータン玉は、やや透明感のある灰緑がかった白色のものが多く、実にぬめやかなやわらかい感じの石で、蛇紋岩やその他の透閃石類と比べて緻密な質を持っています。玉衣に用いられたのもこのテの玉でした。「明一統志」巻89のホータンの条には、「この国には城東に白玉河があって、夜になって月を見てこの白玉を採るし、国城の西の緑玉河からは緑玉が採れる。また城西の三河の源である烏玉河からも年ごとに人が烏玉を採っている。これを撈玉(玉さらえ)という」とあるそうです。多分白玉より緑玉や烏玉の方が沢山とれたのでしょう。
ついでながら、続けて、ホータンの産物に玉、真珠、珊瑚、安息香、水銀、葡萄、獅子などが挙がっています。このうちのいくつかは無論、西方の国々からの交易品がホータンを経由して入ってきたものでしょう。崑崙山脈を含むパミール高原を北に控えたヒマラヤ山脈は、太古インド亜大陸が南方から移動してきて、ユーラシア大陸と衝突した結果生じた褶曲部で、昔は海の底にありました。そのため、山中(ラダック地方のレーなど)で珊瑚の化石が採れ、これを山珊瑚と呼んでいます。崑崙山脈でも採れたようで、崑崙やインドから来た青く美しい珊瑚樹を、中国では「ロウカン」と呼んで珍重したそうです。