鉄と鋼の話 −韮山反射炉の大砲鋳造
先日、伊豆半島をドライブする機会がありました。
うらうらとよく晴れた日。富士山を望む三島駅で車を借り、国道136号線を修善寺方面へ南下。途中、韮山(にらやま)という町に差し掛かった頃、路傍に「反射炉」の看板が眼に入りました。
「反射炉? 製鉄所があったの? どんなところ?」
好奇心が膨らみ、急遽目的地を変更して、見物していくことにしました。
訪れた史跡は、なんとなく明治時代を思わせるハイカラな建造物。案内のパネルによると、江戸末期に作られたものとのこと。白っぽい耐火レンガを積み上げた高さ16メートルに及ぶ煙突が4基、競うように天を衝いていました。往時には白い漆喰で化粧塗りされていたとか。頑丈そうな石垣の上に伊豆石を切って隙間なく組んだ炉体。なかなか見事です。わが国の築城技術は太平の世にも衰えてなかったのだなあ、と感心しました。
以下、韮山反射炉について、鉄と鋼の作り方などを交えてよもやま話風に綴りたいと思います。

この反射炉は、伊豆代官、江川太郎左衛門(坦庵公)が1854年に起工し、3年後、子息の手で完成したものといいます。
坦庵公は、当時頻々と来航していた黒船に対する江戸湾防備のため、幕府に建議して、品川沖に砲台を据え(お台場)、反射炉を築いて、自ら大砲の鋳造にかかったのでした。彼は、日本で初めてパンを焼いてみたり、種痘に取り組んだり、新しい技術に対する鋭い感性の持ち主でした。この反射炉もオランダの技術書に載っていた図面から起草して、独自の工夫を加えながら設計したとのこと。もともと製鉄人ではなかったでしょうから、たいへんな努力の人だったと思われます(これに先立ち、江戸で「高島流洋式砲術教授」の看板を掲げていたので、作り方はともかく、大砲の使い方には習熟していました)。
大砲の製造は、日本では、400年ほど前、大阪冬の陣の際に、徳川家康公が瓦付け法によって鋼片を鍛接して作らせたのが最古とされ、以来、幕府の厳しい統制下にあって、製法上の進歩がほとんどなく、黒船の強力な遠距離射撃をみて大いにあわてたものでしょう。当時の日本には、巨大な砲門を迅速大量に作る技術がなく、南蛮渡来の図版(ヒューゲニンの「大砲の作り方」。1836年に日本に渡って邦訳された)をひも解きながら、ああでもないこうでもないと、国を挙げて製作法を工夫した姿が目に浮かびます。同様の炉は佐賀藩で初めて建造され、次いで韮山(幕府による)、その後、那珂湊(水戸藩)や萩にも作られましたが、完全な形で残っているのは、韮山だけとのことです。
話は前後しますが、私は小学生の頃、子供向け科学雑誌の特集で、「太陽光を凹面鏡で反射させると焦点部に熱が集中して非常な高温になる。反射炉とは、熱を反射集中させることにより、単に燃料を燃やしたのでは得られない高温を作り出して、鉄の精錬を可能にしたもの」というような説明を読んだ記憶があり、そのせいで長い間、反射炉は、巨大な鏡で太陽光を反射させて鉄を溶かすものだと思っていました。これではまるで、ソーラ・レイです。今と変わらない間抜けな勘違いでした。(実際には太陽炉といって、太陽光を鏡で反射させて熱を集中させる炉がフランスにあるそうです)
もちろん、本物は鏡張りではなく、厚く耐火レンガを張った、質実剛健これ我が精神の炉で、内部は下図のような形をしています。
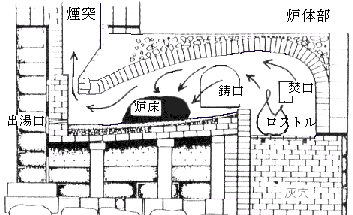
ロストル(火格子・火床)で燃やした石炭の熱を輻射させて、(また熱風を送り、炎で舐めて)、炉床に乗せた銑鉄を溶かします。この間接加熱法は、石炭が直接銑鉄に触れないところが、ミソです。木炭と違い、石炭は硫黄分を含むため、一緒くたにして燃やすと、硫黄が鉄に移って使い物にならなくなるのです。因みに木炭と銑鉄を混ぜて燃やすと、精錬効果があって錬鉄が出来ます。
反射炉は、欧州では18世紀の初めに工業化され、鋳造用の銑鉄を溶かすのに盛んに用いられました。
当時は(銅や青銅など他の金属の鋳造にも)当り前に使われていたものですが、日本ではノウハウの蓄積がありませんから、前世紀の技術の導入でも、たいへんな進歩、大きな飛躍だったといえるでしょう。飛ぶぜ、韮山大シャンツェ!
ちなみに、18世紀後半には、蒸気シリンダーで駆動する送風装置と石炭の組み合わせによって、炉をより高温に熱することも可能となっており、単に溶かすだけでなく、精錬も出来るパドル炉が出現しています。パドル法は、イギリスで発明された画期的な精錬法で、反射炉内に空気を強制的に送り込みながら、溶けた銑鉄を棒でかき回し(パドルし)、ロストルから炉床に這い昇る高温の酸化炎で脱炭してゆくものです。
「大砲の作り方」は、銑鉄(鋳鉄)からの鋳造法を述べたものなので、パドル法そのものへの言及はないそうですが、「銑鉄を反射炉に入れ、激しく火をたいて溶かせば、非常に粘り強い質の鉄に変わる。鉄の中に含まれる炭素やその他の混雑物を排除することによって、砲身の質を堅く剛くすることが出来るのだ。」、「時間をかけて溶湯をよく攪拌しなければ、大砲にもろい部分が出来てしまう。」などとあり、大砲鋳造用の反射炉が、単に鉄を溶かすだけではなく、炎を駆使して鉄の性質をより優秀にすべきものだったことがわかります。坦庵公も、そうした錬金術的な反射炉の作用に強く魅せられたことでしょう。

鋳口

出銑口
日本で作られた大砲が、世界的に見てどんな水準のものだったかを知るため、鉄の性質と当時の製鉄技術について簡単に触れておきましょう。
鉄鉱石は木炭とともに燃やすことで、還元されて鉄になります。純粋な鉄は1500度以下の温度では溶けませんが、固体のままでも還元できる(400度〜800度で反応が進む)ので、鉄の利用は比較的早い時代(紀元前)に始まったと考えられています。
燃焼が進むと、鉄は炭素を吸収して、融点が下がり、1200度前後で溶け出します。これは木炭をうんとこせっせと燃やすと達成可能な温度です。こうして炭素を(4%くらい)含んだ鉄が銑鉄(鋳鉄)です。鍛造は出来ませんが、鋳物を作ることが出来ます。
銑鉄を木炭で熱して溶かし、過剰な空気(酸素)を吹き付けると、吸収した炭素が燃えて鉄は再び固まり始め、粘りのある錬鉄(可鍛鉄または軟鉄)に変化します。加工性のよい軟らかい鉄です。銑鉄から錬鉄に至る中間のどこか、つまり炭素の含有率がその間の特定領域にあるとき、鉄は、強靭で硬く、鋳造も鍛造も出来る理想的な状態になります。しかも焼き入れ・焼戻しという特殊な熱処理が可能になります。これが鋼です。鋼は銑鉄より融点が200度ほど高いので、この温度差がクリア出来るまで、人類は溶けた鋼を眼にすることがありませんでした。これがほかの金属との違いで、鋼だけでなく、西洋では、高炉が発明されるまでの長い間、鉄は(銑鉄も錬鉄も純粋な鉄も)溶けない金属だと考えられていました。
その昔、まだ1000度程度の温度しか作り出せなかった頃、鉄鉱石は固体または半溶状(ルッペ)で還元され、丁寧に鍛錬して不純物を取り除き、錬鉄とされました。いまでもアフリカなどの自然民族は、この方法で鉄を得ています。こうして鉄鉱石から直接、錬鉄をつくる方法を直接製鉄法と呼びます。対して、いったん高炉で溶けた銑鉄を作り、改めて精錬炉で脱炭して錬鉄(鍛鉄)を作るのが間接製鉄法で、時代が下ると生産効率の良い間接法が、直接法を圧倒するようになります。
欧州では、15世紀頃、水車を使って強制的に空気を送り込み、木炭の燃焼を促進させて高温を作り出す技術が確立し、高炉が生まれます(14世紀に萌芽あり)。高炉の発明により、溶けた銑鉄(溶銑)を大量に作ることが出来るようになりました。高炉は、燃料の木炭が入手しやすい森林地帯を控え、水車を回せる川がある土地に建造されました。木材資源が豊富だったイギリスでは、ウィールドの森やセヴァーン川流域などに製鉄工場が立ち並びました。そして銑鉄を鋳込んだ大砲をじゃんじゃん作り、16世紀にはスペインの無敵艦隊を撃破、大国への足がかりを得ます。これが鋳鉄砲の始まりです。
製鉄は大量に木炭を消費します。イギリスでは、その後、製鉄業の急速な発展が深刻な森林資源の荒廃をもたらしたため、一時はスエーデンやドイツから鉄を輸入せざるをえなくなります。木炭依存から脱し、石炭製鉄への転換が模索され、18世紀に至って、石炭の蒸し焼き(コークス)を燃料とする高炉が実現。さらに蒸気機関の発明によって送風装置が整い、より高温で鉄を扱うことができるようになりました。石炭を燃料にした反射炉が工業化され、銑鉄の再溶解、そしてパドル法を併用して錬鉄を精錬することも出来るようになりました。イギリスは、再び製鉄立国として活力を取り戻します。鉄道の敷設が、鉄の消費を格段に増やしました。
上述のように、欧州では、初め、高炉から直接鋳込んで大砲を作りましたが、時代が下ると反射炉で銑鉄を溶解して鋳造することも始められました。2度手間になる反射炉を使う理由は、そもそも高炉から直接銑鉄を鋳込むには大砲が大きくなりすぎたことですが、どこかの国の誰かが優秀な鉱石から製造した高品質の銑鉄を買ってきて鋳造出来ることも大きな利点だったといえます。当時は、スエーデンの木炭銑、オーストリアのシュタイエルマルク銑などに定評がありました。また、上述した「大砲の作り方」にある通り、若干の鋼質化を狙うことも視野にありました。つまり、再溶解によって、高炉銑鉄よりも純度が高く(不純物をスラグ化して除去)、均質で、炭素分が少ない(ねばい)鉄を作ることも可能だったのです。坦庵公が高炉でなく反射炉を選択したのも、おそらく、日本古来の製法で作った和鉄(和銑)を反射炉でさらに練り上げようと考えたのでしょう。あるいは、単に高炉の建造にはお金がかかり、技術的にも(銑鉄の製造ノウハウを含め)困難だと考えたのかもしれませんがね。
さて、坦庵公が炉の試作を始めた1849年は、欧州ではこれら一連の技術革新が一段落し、高炉による銑鉄の大量生産、パドル炉による錬鉄の中量生産、るつぼ製鋼による鋼の少量生産が実現していました。そして、数年のうちに、錬鉄や鋼鉄の大量生産を可能とする画期的な新技術が出現する端境期でもあったのです。
いま、まさに鋼の時代が幕を開けようとしていました。ドイツのクルップ社が、製鋼るつぼを100個も連ねて、それまで不可能とされていた巨大な鋼の塊を作り出し、ロンドンで開かれた万国博覧会に、強靭な鋼鉄製の大砲を出品したのが1851年。数年後にはイギリスの天才発明家ベッセマー氏が、鋼も錬鉄も思いのままに大量生産できる「空気底吹き(吹精)転炉」を発表。これを受けて、スエーデンではダネモラ(ダンネムーラ)鉱石を使った優秀な鋼が誕生します。ドイツのシーメンス兄弟によって、反射炉に蓄熱室を組み入れた熔鋼炉(平炉)が考案されたのが1856年。これらの新技術は、当初使用可能な鉱石や銑鉄が限られていたため、パドル法の天下はまだまだ揺るがなかったとはいえ、時代は明らかに鋼鉄の大量消費へと推移していました。そして、1879年、裁判所書記のトーマス氏が塩基性耐火レンガを開発し、新しい製鋼法のアキレス腱だった燐の効果的な除去法(あと吹き)を発表すると、フランスやドイツでもミネット鉱石を使った鋼の大量生産が始まり、アメリカも含めて本格的な鋼の時代が到来するのです。19世紀の後半は、有史以前から行われてきた製鉄が、量子飛躍的な技術革新を遂げた時代でした。
韮山の反射炉は、こうした鉄鋼革命の前夜に着手されたわけで、当時としてはオーソドックスなものだったとはいえ、ほどなく欧州で開発される新技術からは、はるかに遅れをとる運命にありました。韮山反射炉は、ほぼ7年間操業され、大砲数百門を鋳造してその役目を終えました。(実際には、大半が青銅鋳砲で、鋳鉄砲は、ほとんど作られなかったとか。−末尾の追記を参照)
勢威を誇った鋳鉄砲は、欧州では数年のうちに、ケーシング法を取り入れた錬鉄砲に、あるいは、より性能の良い鋳鋼砲にと進化してゆくのですが、これについては最後にもう一度触れることにしましょう。
次に、大砲の製造に使われた原材料に目を向けてみましょう。
まず燃料ですが、基本的には石炭を用いました。筑後や常磐から持ってきたようです。石炭は木炭以上の高温を作り出すことが出来ますが、鋳造の場合は、その高い熱量を正しくコントロールする技術が要求されます。炉の温度を素早く上げるため、空気をどんどん送り込んで炎を盛んにすると、精錬反応が進行して、湯流れが悪くなり(融点が上がるため)、鋳込みがうまくいかなくなるからです。スカル(後述)が発生して歩留まりも悪くなります。この現象は、パドル炉精錬の原理をなす大切な要素であり、鉄に粘りをもたす効果もあるのですが、ひとつ間違うと却って悪影響を及ぼすことがあったのです。反射炉では、燃料の下部と、上部に通風孔があり、必要に応じて開閉して空気(酸素)の混合比を調整し、還元炎や酸化炎を作り出すようになっていますが、通常は炉を締めきって送風を控え、必要以上に温度を上げないことが大切でした。通風を落とし炎を還元性にして炉内温度を保ち、対流効果で湯を十分に練って成分を均一化、溶湯の粘りをコントロールするというノウハウも知られていたようです。なお、石炭の底には木屑や薪を敷いたとのことです。(ヒューゲニンは反射炉の燃料として石炭を指定しており、それ以外の燃料を使用するときは、別の設計とするよう注意しています。佐賀藩は当初木炭を使った鋳造を試みて失敗を繰り返し、1853年、17回目のトライでようやく成功。おそらく筑後産の石炭を使ったものと考えられています。その3ケ月後、韮山から八田兵助がノウハウ取得のため佐賀を訪れました。韮山ではすでに伊豆天城の木炭1万俵を用意していたのですが、八田の意見により筑後の石炭10万斤を取り寄せ使用したということです。)
一方原料となる銑鉄は、どこからもってきたのでしょうか。明確な資料が手元にありませんので、勝手に想像してみますと、まず名高い中国地方の砂鉄銑が思い浮かびます。しかし、ある資料によると、「佐賀県の反射炉では、当初、中国地方の砂鉄銑を使っていたが、スカルを多量に形成してうまくいかなかった。そこで長崎に入港する船のバラスト(重しの鉄)を使ったところ、スカルがあまり発生せず具合がよかった」、とありますから、韮山でも同様に輸入銑鉄(洋鉄)を用いたかもしれません。
(日本の伝統的なたたら製鉄による砂鉄銑は、しばしば嵩上げのため、生の砂鉄を銑鉄に混ぜるような操業が行われました。そのため品質の劣る製品が多かったようで、この種の鉄は到底大砲に用いることは出来ません)

最もたくさん鋳造された、24ポンドカノン砲

ちなみに、1855年、那加湊に反射炉を作り、大砲数十門を鋳込んだ大島高任という人は、「従来のような砂鉄銑で大砲を作っていたのでは、どうしても外国の大砲に太刀打ち出来ない。優秀な鉱石を高炉で溶かして質のいい銑鉄を作らなければならない」と悟って、釜石(正しくは南部藩大橋)に高炉を作り、1858年には出銑に成功(日本初)していますので、これ以降は、こちらの銑鉄を使った可能性もあります。現にこの年の春、高任は2700貫の高炉銑を那珂湊へ送っています。ただし、那珂湊ではこれを使って大砲を作ったものの、水戸藩を揺るがす政争が勃発したあおりで、試射を待たずに反射炉もろとも打ち壊されてしまったといいます。(高任の高炉も、例のヒューゲニンの本を参考にして建造されました。坦庵公も、高任も、読書家だったのですね。当時、外国の技術や知識は、書物から仕入れるよりなかったのでしょう。)
先ほど、説明なしにスカルという言葉を使いましたが、これについて補足しておきます。
製鉄の過程というのは実に不思議なものです。理論が解明された今でもそうですが、当時の日本のように、正確な化学反応の法則が、いまだ神秘のベールに覆われていた頃は、なおさら畏怖の念に満ちた作業だったことでしょう。炉の底に炭をくべ、どんどん炉を熱くする。空気をばんばん送って燃焼を早め、さらに温度を上げる。やがて挿入した銑鉄が、どろどろに溶け始めます。炎になめられ、白熱光を発しながら渦巻きます。新鮮な空気(と炎の中の酸素)に触れた鉄は、わけのわからない反応によって性質を変え、次第に粘っこくなり、煮えたぎった湯の表面にはやがてスープ膜のようなスラグ(滓)が浮かび上がってきます。炉壁に飛び散った溶銑は、表面が鋼に変質して固まり、内部は銑鉄のままなので流れ出し、結果的に中空の鉄の抜け殻が出来ます。これがスカル(またはスケルトン)です。いかにスカルを作らないようにするかが、当時の職人の腕の見せ所。経験と勘によって適当な銑鉄、不純物の除去剤、燃料を選択し、温度と時間の兼ね合いを決定していったのです。
しかし、見方を変えれば、スカルは鋼質化した鉄です。パドル法は積極的にスカルを形成し、すべての鋳鉄をスカルに変えるという発想から生まれました。だから、もし日本で、鋳鉄でなく錬鉄、あるいは鋼鉄を作ろうと考えたときには、鋳鉄砲の製造では嫌われた砂鉄銑が、むしろ重宝がられる可能性もあったわけです。鉄というのは本当に不思議な生き物です。
最後に、日本と欧州の大砲の比較です。
日本で鋳鉄砲が作られた頃は、欧州でも同様の大砲が幅を利かせていました。しかし、鋳鉄は固いわりに脆いところがあって、発射時の衝撃が重なるうちに、内部欠陥を起点にヒビが入ったり、破裂する危険がありました。鋳鉄砲は鍛造できないので、素材である銑鉄の品質が何より大切です(もちろん鋳込みの仕方も大切)。その点についての評価は、上述した高任の言葉が状況を説明しているように思います。
一方、欧州では、この頃から鍛造可能な鉄を用いた大砲が姿を見せはじめます。ドイツでは1860年以前に、クルップ社が粘りがあって破断しにくい鋼鉄製の大砲を作り、ドイツ軍などに供給をはじめました。クルップ鋼は、るつぼ製鋼のため、結構値段が張ったようです。
一方、予算のない(?)イギリスでは、錬鉄を用いたアームストロング砲が開発されます。これは、サイズの違う筒をいくつも嵌め込んで一体化したケーシング構造で、外側の筒の内径を、内側にくる筒の外径よりやや小さく加工するのがミソです。外筒を熱して膨張させてから内筒を挿入、鍛接します。筒が冷えると外筒が収縮して内筒を締め付け、筒の中心に向かう応力を発生します。これが火薬の爆発による外部へ向かう圧力と相殺し、より多くの火薬が使える、頑丈で強力な大砲となるのです。イギリス海軍が、初めてアームストロング砲を大規模に投入したのは、1863年の薩英戦争でした。旗艦には110ポンド巨砲が搭載され、鹿児島の町を焼いて戦果を上げました。けれども、機構の複雑な後装式(弾を後ろから篭める)だったこともあり、故障が多かったので、ほどなく前装式に戻して、安価なベッセマー鋼を使った鋼鉄砲に置き換えたということです。そもそも砲弾を高速で射出する最内筒にまで、軟らかい錬鉄を使ったのは、根本的な間違いだったので、摩滅に強い鋼に置き換えたのは当然のことでした。
ともあれ、日本の鋳鉄砲(多くは24ポンド砲?)は、鎖国以来の技術的空白を一気に取り戻すものでありながら、鋼の時代に向けて急発展を遂げた欧米の鋳鋼砲には敵しえなかったのでした。後に明治維新政府の下で、クルップ砲が海軍に採用され、やや遅れて陸軍も追随するのですが、これはやむを得ない選択だったのでしょう。
高炉の発明以来、300年以上蓄積された技術の上で大砲を作っていた欧米列強に対し、技術書1冊から炉を建造し、大慌てで製鉄技術を学び始めた日本。以来、明治政府の殖産政策に乗って、シーメンス法平炉で腕試し、1894年にはコークスを使った高炉製鉄、次いでベッセマー法を発展させた転炉を導入、急速に欧米の技術水準に接近してゆきます。そして数次にわたる戦争経験を経てノウハウを取得、二次大戦後は、それまで圧倒的に多かった平炉からLD法(酸素上吹き)転炉への大転換を敢行、連続鋳造技術を積極的に取り入れて、世界の製鉄をリードするまでになってゆきます。その長い道のりを短期間に踏破したことを考えると、並大抵でない先人の苦労が偲ばれます。韮山の反射炉は、こうした歩みの最初の1歩だったのだなあと、感慨もひとしお深まります。
おわり(2000.4.1 SPS)
(revise on 2001.3.17)
(画像差替え 2024.3.3)
■韮山での鉄製大砲製造数について 追記:本文作成後に知った情報を書いています。これを書いたとき思っていたイメージと違って、実はこの反射炉は、ほとんど実用段階に達しなかったようです。詳細はこちらに。
備考1:韮山の反射炉の詳細については、坂本さんのホームページにお世話になりました。大砲の写真は、氏がわざわざ撮って下さったものです。氏のホームページには、反射炉の詳しい写真もありますのでご覧下さい。(他にも猫の博物館とか伊豆周辺のスポット案内などがあります。)
備考2:文章中の「銑鉄(鋳鉄)」、「錬鉄(鍛鉄、軟鉄)」、「鋼(鋼鉄)」の区別は、当時の概念で、現在の定義とは必ずしも一致しません。(現在は錬鉄と鋼をひとくくりに鋼鉄とし、炭素量によって、軟鋼、硬鋼など5,6種に細分しています。)