ボルネオ島のコタ・キナバルからクアラ・ルンプールに向かう飛行機が、マレー半島の上空にかかったとき、眼下に異様な風景を見た。このあたりは典型的な熱帯雨林地帯で、普通なら、なだらかな山地を濃い緑色の絨毯がべったり覆っているはずなのだが、その中にところどころ禿げて白茶けた、剥き出しの大地が見えたのである。土地と森の境界は線を引いたように鮮明で、人の手が加わっているのは明らかだった。ところが、その範囲には人工的な建造物はひとつもなく、あるいは一本の木すら生えていなかった。しかも、どうやってたどり着くかも知れない深い森の中である。一体何の跡なのだろう。それとも、これから何かを作る場所だろうか。飛行機が空港に着陸するまで、この奇妙な景色が飛び石伝いに点々と続き、私はすっかり気持ちを乱されてしまった。
クアラ・ルンプール到着後、現地に駐在している商社の方々に、あの景色は何だったのかと聞いてみたが、はっきりしたことは分からなかった。最近出来たものではないようだ。しかし、ガイドさんのお話を聞き、また帰国後、本を読んで調べるうち、どうやらかつての錫鉱山に関係したものらしいと思うようになった。今はすっかり衰退しているが、ほんの15年ほど前まで、マレー半島は世界有数の錫(以下スズと書く)の産地であった。山地や河口付近には至るところ鉱山が稼働していた。マレーシアの首都クアラルンプールは高層ビルの立ち並ぶ近代都市だが、発祥は19世紀後半にスズを採掘するために開発された鉱山町で、ここから河口部の海港クランへ鉱石を運ぶ鉱山鉄道は1886年に開通している。郊外にある某社の工場へ向かうバスの中で、ガイドさんが、「あれは鉱山の跡です」と指した場所は、幹線道路沿いの荒地にあった。「スズを掘った跡は、クアラ・ルンプールの周囲に沢山あります。何十年たっても木も草も生えないです。あそこは水がたまって池になっています。」と言う。
私が飛行機から見たのは、そうした跡地の連なりだったのかもしれない(しかし、今のところ確言は避けておく−ほかの可能性もあるから)。
というわけで、私はスズに興味を持った。今回は、マラッカ(以下、本文では、主にマレー半島、スマトラ島およびその周辺の島々を指すものとする)でのスズ採取の歴史を振り返りながら、マレー半島の自然と住民の生活に、スズ鉱山がどれほど大きな影響を与えたかについて書いてみた。にわか勉強のため、教科書的な内容になってしまったが(おまけに長い…)、ご興味のあるところを適当に拾って読んで下されば幸いである。
※マラッカは、マレー半島の町の名前であり、ここを拠点とした王国の名前であるが、本文では別の定義をさせて頂いた。町として使う場合は、マラッカ(都市)、国の場合はマラッカ王国として区別する。
◆まずスズについて。
★スズは人類史に大きな役割を果たした金属である。その始まりは有史以前とされている。比較的単純な技術で、鉱石から精錬できるため、古くから知られていたのだろう(※脚注1)。鉛に次いで柔らかく、融点が低くて加工しやすいので、さほど強度の要らない生活用具を作るにはもってこいの素材だ。単体で、あるいはスズを主体とした合金(例えば鉛やアンチモニーを混ぜたピューターなど)として重宝されてきた。しかし歴史的により重要なのは、銅合金あるいは鉄複合材としての側面である。
かつて青銅器文明が勃興した頃、スズはその一方の原料として重要な鉱物だった。人類の金属史は金・銀に始まるが、生活用器として真に重要な存在になりえたのは、大量に(かつ安価に)入手可能な青銅(銅)や鉄だった。例えば中国においてはBC13世紀以前に、すでに高度の青銅器文明が展開されていた。伝説的にはBC3000年前後に遡る。ヨーロッパ・中東もその頃に前期青銅器時代を迎えている。青銅は銅にスズを1〜30%の範囲で加えた合金で、成分比を調整することで、用途に合った適当な性質のものが得られる。総体的に銅に比べて融点が低く(銅は1085℃、青銅は1000〜700℃前後)、鋳造が容易で、しかも冷却後は銅よりも硬くなる。農耕具や武器としても優秀であった。銅と違って、刃を作れるのが大きい。青銅器(あるいは鉄器)文明の誕生は、農耕文化の高度な発展をも意味している。
大量の鉄が生産されるようになると、青銅で作られていた器物の多くは急速に鉄器に変わっていった。青銅の衰退に伴って、スズの消費もまた後退した。しかし、日用品(食器など)の素材としては依然一定の需要があった(※脚注2)。中世期以降になると、スズには別の重要な役割が賦与される。鉄は青銅より安価で、かつ硬度も高いが、錆びやすいという重大な欠点がある。その対策にスズが役立った。鉄板の表面に塗膜(メッキ)すると、防錆効果のあることがわかったからだ。そうして開発されたのがブリキである。ブリキは鉄の強度とスズの美しさ、そして防食性(特に有機酸に強い)を兼ね備えた複合材だ。初めてブリキが作られたのはボヘミア(ベーメン)で、1240年頃のことだったと言われる。年代については14世紀あるいは16世紀という説もあって定かでないが、古くから鉱山が開かれ、12世紀には開花期を迎えていたボヘミア地方に発したことは疑いない。ここはヨーロッパ錬金術の故郷ともいえる土地だ。製造技術は、17世紀の始め、サキソニー侯によってザクセン地方にもたらされ、やがてイギリスやフランスにも伝えられた。長い間、ブリキは主に食器用に使われていたが、19世紀の半ば以降、幅広い用途が見出されて生産量が急増した。クリミア戦争やアメリカの西部開拓、南北戦争の影響で、石油缶や缶詰の素材、屋根材などに需要が膨れ上がったのであった。(ブリキ缶詰は、1810年にイギリスで特許が申請されている。ナポレオンが遠征食糧の保存法を公募したのがきっかけで、びん詰めが発明され、その技術を応用したものという)。缶詰がなければ、戦争用の保存食がなく、大規模な戦争の遂行も困難だったろうというお話だ。
なお現在では、電気部品を接合するハンダ材としての需要も大きくなっている。
★ところで、金、銀、銅、鉄などに比べ、スズは産地の限られた金属である。その埋蔵量は全世界で770万トン以上と推定され、決して少なくないのだが(年産20万トン強)、大きな鉱床は、東南アジア、中国、南米大陸、オーストラリア、イギリスなど特定の地域に偏在している。事情は古代においても同じだったから、スズのない土地では青銅器文明は生まれなかったろうという見方も出来る。実際いくつかの文明は、交易や略奪によってスズを手に入れるまで青銅器の存在を知らず、もっぱら銅器や鉄器を使用していた。
一般に青銅器時代は鉄器時代に先立つとされているが、どこでもそうとは限らないわけだ。なお、この二者のいずれが先に実用化されたかは議論の分かれるところで、鉄や銅は広い範囲で採集可能だが、青銅を作るには、スズの確保という課題をクリアしなければならない(※脚注3)。従って青銅より鉄の方が先に見出されたという説もある。最古の鉄製品は今のところ、BC5000年頃のものとされるイラク・サマラの出土品で、確かに青銅器時代に先駆けている。ただし銅製錬はそれより早い。
エジプトやメソポタミアに青銅器をもたらしたスズはコーカサス地方(またはトルクメン)から、ヨーロッパではドナウ地方(ボヘミアを含む)から、後にはイギリスから供給され、各地で豊富に採れる銅に結びついたと考えられている。古代中国の青銅器文化は、おそらく初期には中央アジア、やがて中国南方やマラッカのスズに支えられたと見られる。
このような産地の偏在性のため、スズを産出する土地の支配、鉱山の開発、交易といった事業は、大きな利益を生み出すものであった。
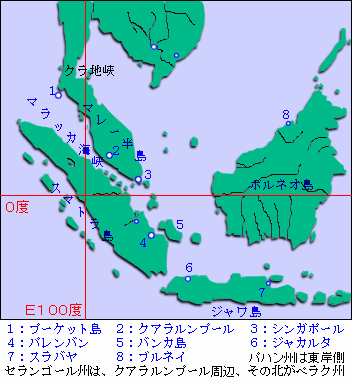
◆さて、マラッカは地理的に東の中国と西のインドを結ぶ東西交通の要衝である。大陸から太平洋へ向けて南下する民族移動の道でもあった。スマトラ島とマレー半島とに挟まれた水深の浅いマラッカ海峡は、東西南北がひとつに交わる十字路であり、文字通り、モンスーンが始まり、終わるところであった。この地を境に風が変わった。海峡を渡る交易船は、次の海へ船を進めるために、ここで風待ちをしなければならなかった。逆風を待って、元の航路を引き返す者もいた。その昔、インドとマラッカ海峡を往復するには、少なくとも2年かかった。世界中からきた商人と物産は、必然的にこの地に集まり、留まり、また旅に出なければならない。マラッカは通過点であり、会合点であり、また中継点であった。古くから交易社会としての性格を持っていた。
★その歴史を簡単に辿ってみよう。マラッカは少なくとも紀元前500年頃から、インド人の間で、ある種の楽園とみなされていた。スズの採集は当時から行われていたが、それよりも黄金の地として有名だった。インド人たちは、この地に砂金を求めて、また象徴的な意味での黄金、つまり豊かな生活を求めて、海を渡ってきた。マレー半島内陸部のパハン、ボルネオ西岸、スマトラ島のミナンカバウなどが古くから知られた金の産地で、彼らが「ヤーヴァドヴィーパ」(大麦の島=黄金の島)と呼んだ土地は、現在のジャワ島に比定されている。私見だが、この島の名前が中国に伝わり、東海に浮かぶジパングの伝説になったのではないだろうか。インド人にとって東方の島はジャワだが、中国人には日本が東の蓬莱島にあたるから。(正説では、日本国という語を元代中国の発音で読めば、ジィパンクゥ−jihpenkuo−であって、マルコ・ポーロは正しくその名前を伝えたと考えられている。因みに、9世紀頃のイスラム書には、日本はワクワク(Waqwaq)の名で出てくる。倭国の訛りといわれている。)
マラッカの評判は、紀元前後にはヨーロッパにまで達した。AD2世紀にギリシャのプトレマイオスが作成した地図には、マレー半島がクリス(黄金)の名で記載されている。流れる河は黄金河である。以来、今日でもマレー半島を、雅語で黄金半島と呼ぶ。砂金は、2000年以上にわたってマラッカの重要な交易物資だった。金の採集は現在も続いているが、そのことには後でまた触れることにしよう。
500〜1000年に渡って庶民層の流入が続いた後、インド支配者層が渡ってきた。当時、交易の拠点は、マレー半島の付け根、クラ地峡周辺にあった。この地の水田耕作(米作)による余剰食糧が交易者や移民を惹きつけたとみられ、AD3世紀にはベトナムにインド色の濃い王朝が誕生している。マレー半島の内陸部はいまだ深いジャングルで、沿岸部(特に西側)はマングローブ(ワニとマラリア蚊の棲処)に覆われていた。この時代の記録は少なく、定かなことはわからないが、人々は腐海のほとりとも言える河口や河川周辺のわずかな平地に住み、自然の与えた豊かな物産を採集し、クラ地峡の交易都市に集散させたのだろう。なお、ミナンカバウやジャワ東部もまた、水田耕作に適した土地で、インドの影響を受けた農耕文化の揺り籠となった。詩聖タゴールは、インド文明が東南アジアにあふれたこの時代を、郷愁をこめて詠っている。
−ジャワへ−
記録も残さない はるかな昔
あなたと私は 出逢った
私の言葉は あなたの言葉に
私の生命は あなたの生命に混じりあった
東風はあなたの招き声を
見えない風の流れに乗せて伝えた
陽の輝く遠い浜辺で
風にざわめく椰子の葉が招いていた
招きの声は聖なるガンジスのほとりで
神々の祭壇を祝ぐ ほら貝の音と響きあった
ヴィシュヌ大神とパールヴァ女神は私にこう命じた
「船を整え わが崇める教えを携えて 未知の海を渡れ」と
東方への憧れは近世に至るまで続いた。1820年以降、大勢のインド人(タミール人、ベンガル人、セイロン人など)が組織的にマラッカに送りこまれ、砂糖キビ農園で働かされた。その多くは流刑者(思想犯も多い)や貧民たちで、後にゴム農園を支える労働力となっている。彼らはマラッカを黄金の島と信じて海を渡ったが、現実には厳しい労働の明け暮れが待っていたのだった。
★マラッカ社会の特徴のひとつは、交易に従事し、海洋民を使役した沿岸部社会と、農耕を主体とした内陸部社会との二重構造が、19世紀に至るまで、あらゆる時代に存在していたことである。むしろ両者の葛藤と包摂がマラッカ史の推進力であったといえようか。
前述のように、ジャワ島東部、スマトラ島の西側中北部、クラ地峡といった地域には、水田耕作が可能な平野部があり、古くから農耕社会が成立していた。ジャワ島では8世紀にシャイレンドラ朝が興り、13世紀にはマジャパイト朝が成立して強盛を誇った。彼らはしばしば隣接する交易社会に侵攻し、さまざまな影響を与えた。スマトラ島のミナンカバウは、19世紀前半にオランダに屈するまで常に独立を保った強国だった。
一方、マラッカ海峡の両側は、マングローブとジャングルの繁茂する土地で、耕作には不向きだった。人々は沿岸部に住んで漁業や交易や海賊行為に携わった。漁業は狩猟経済であり、不安定要素が大きい。不漁が続くと、いきおい略奪に走らざるをえなかった。マングローブの入り江は格好の隠れ家で、彼らは、そこから足の速い小舟で出撃し、海峡を通過する交易船や沿岸に住む他部族集落を攻撃し、略奪した。農耕社会と違って土地そのものが価値を産まない交易社会では、戦争と略奪は常に交易品と人間労働力を巡って行われた。実際、奴隷はマラッカ交易社会の重要な商品であった。人的消耗がきわめて激しかったからだ。
(ちなみに、19世紀、イギリスのラッフルズ卿が、マレー半島のサルタンに、「略奪のような恥ずかしい行為をやめて通商に力を入れてはどうか」と勧めたとき、「略奪は先祖代々の仕事で、少しも賤しいものではない」と返答されたという。)
もちろん皆が皆、略奪に走ったわけではなく、大抵の部族は、平時には略奪より交易に精を出すのが常だった。海峡は(ルートはいくつも考えられるが)、あらゆる交易品と商人が通過せざるをえない場所だ。自国の勢力圏を安全に通行する見返りとして、交易の多寡に応じて通行料を徴収するシステムは、ごく古い時代から成立していた。そもそも自分の家の庭先を無関係の不審人物が我が物顔に通って、またそのことによってボロ儲けをするなんてことを許せる人間があろうか。略奪にしろ、中継貿易への参加にしろ、あるいは通行税の徴収にしろ、これらはごく自然な人間的行為から始まったものである。そこで問題は、双方にとってどの手段がもっとも望ましいかというレベルに帰着させることができた。通行税制度は交易商人にとっても、沿岸部族にとっても、望ましい取り決めだった。お互い命を危険に曝す必要がなかったからだ。また安全な通行の保障は、そのルートを通る交易をいっそう盛んにさせる効果もあった。もっとも、海峡を通過する間に、複数の相手から、小刻みに課税された挙句、最後に第三者に略奪されたのではたまらない。交易が発展するには、海峡を一手に押さえる強大な国家の出現が必要だった。
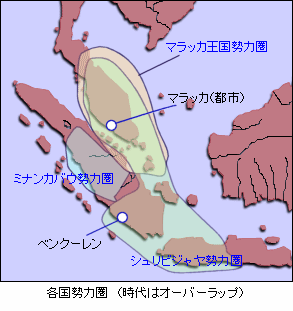
★海峡を完全に掌握した最初の国家は、AD7世紀に成立したシュリビジャヤである。彼らは、スマトラ島のパレンバンを本拠地とし、マレー半島に至る広い範囲を勢力圏に収めた。シュリビジャヤは14世紀まで続いた典型的な交易国家だった。自給食糧をほとんど持たず、中継交易によって得た利益で、ジャワやミナンカバウなどから米を調達した。根幹となる労働者は外国商人と土地の海洋民だった。海洋民たちは、支配者層と一定の労働奉仕契約を結び、見返りに食糧や略奪のアガリを受け取った。一方、支配者である王侯貴族たちは、交易による利潤とその管理権を主な収入源とした。この2者と外国商人が事実上、王国を構成する国民のすべてで、生産者たる農民層は不在であった。シュリビジャヤの伝統は、1403年、マレー半島に興ったマラッカ王国に引き継がれた。マラッカ王国もやはり農耕基盤を持たない交易国だったが、イスラム教を積極的に取り入れ(おそらくイスラム商人との協調と王家の権威確保のためだろう)、ほぼ一世紀に亘って繁栄した。いわゆるマラヤ(貴族)文化が醸成されたのは、この時期である。マラッカ王国は、1512年にポルトガルに追われてジョホール(リオウ島)に落ち、以後勢力を弱める。しかしマラッカの正統な後継者とみなされた(王家の神器を受け継いだ)ジョホール朝の下で、マラヤ文化は、19世紀半ばまで残光を放ち続けた。ジョホール朝は17世紀末に王の血統が絶え、18世紀にはその支配力を弱める(以後、正式に神器を継承する皇統が途切れた)。そのため、各地方のサルタンたちは、オランダ、イギリスなどを巻き込み、土地管理権を巡って果てもなく紛争を続けた。結局、この世紀中、海峡の通行管理権を握る大国は現れなかった(オランダは別)。諸国は交易のカスリを奪い合い、内陸部の生産は発展しなかった。
★話はやや遡るが、ポルトガルがマラッカに商館を建てたのは1511年のことだった。西欧諸国が直接アジアとの交易に乗り出したのはこれが嚆矢で、次いでスペイン、やや遅れてオランダが船団を送ってきた。制海権争いの末、ポルトガルとスペインは戦列からはずれ、代わって17世紀から19世紀にかけて、オランダとイギリスが、マラッカで勢力を争った。オランダはまずジャワ島を軍事力で押さえ、1641年にはマラッカ(都市)を攻略、海峡交易を支配した(他の国々はオランダの勢力が及ばないクラ地峡やジョホールを抜け道にした)。彼らはイギリスにほぼ一世紀先がけて植民地化に取組み、ジャワやスマトラで、換金性の高い外来作物の栽培(さとうきび、藍、キニーネなど)を始めている。スズの採集も最初から国営で行われた。マラッカのスズがオランダ東インド会社の手で、初めてアムステルダム市場に送り込まれたのは、1667年のことである。オランダは、サルタンたちと契約を結び、一時スズ交易を独占した。18世紀初めには、バンカ島でスズ鉱が発見された。いわゆるバンカスズの興りだ。ビリトン島、シンケップ島でも採取が行われた。当時、交易船の積荷は、モルッカの香料、インドの綿花など軽いものが多かったから、ヨーロッパへ帰航するオランダ船にとって、重たいスズはバラストとしても具合がよかった。島嶼インドネシアのスズ鉱山は、早くから地歩を固めていたのである。
★イギリスの商館がスマトラのベンクーレンに開かれたのは、1684年。インドに手間取り、進出がやや遅れたものの、本国−インド−中国を結ぶ三国間交易の中継地として、マラッカはイギリスにとっても重要な戦略拠点であった。
ところで、海峡を支配していたオランダ東インド会社は、18世紀を通じて、常に赤字状態だった。戦費が利潤を上回ったのである。イギリス東インド会社も台所事情は同じで、稼いだ利益は早晩アジアやインド内陸部への派兵費用に消える運命にあった。一方植民地官僚たちはといえば、会社の赤字を横目に見ながら、莫大な財産を倦むことなく蓄え続けていた。特権で交易船に積み込んだ私的物資を捌き、容易に利益を得たのだ。そうした背景にあって、18世紀中頃には、カントリートレードと呼ばれるイギリスの私商船が、盛んにマラッカに出没している。彼らの多くは、コーンウォール出身の気の荒い船乗りたちで、インドに本拠をおき、中国との間の各国を巡航した。冒険心に富んだ船長たちの中には、インド・マルワ産のアヘンをマラッカや中国に運んで、一財産築いた者も少なくなかった。18世紀末、広東に集まるイギリス船は、他国船の総数を上回っている。彼らは、毛織物、インド木綿、アヘン、鉄、スズ、各種香料を運び、中国の茶、絹、陶磁器を持ち帰った(輸入高の半分が茶)。1814年に独占権が撤回されるまで、中国との交易は東インド会社が一手に引き受けていたのだが、アジア内での商売はまた別の話だった。植民地官僚は率先して私商船の便宜を図り、商品を委託して私財を稼いだ。政情不安なアジアの海には略奪者が横行し、リスクが大きかった。交易船は当然武装しており、チャンスがあれば自身海賊に早変わりした。国家間の紛争と、略奪行為の境界はきわめてあいまいであった。
★1824年の英蘭協定によって、マラッカにおける植民地の分割が確定した。マレー半島西岸とスマトラ島東岸は、歴史的に同じマラヤ文化圏にあったが、海峡を境に東はイギリス、西はオランダに分断された。オランダのマラッカ(都市)とイギリスのベンクーレンが交換された。英領シンガポールが承認され、海峡の自由通航権が認められた。戦争に疲弊したオランダ本国と、産業革命以後躍進著しいイギリスの力関係がここに反映されている。以後、イギリスは安心してマレー半島の経営に参画していった。19世紀は遅れていた半島内陸部の開発が進み、社会体制が大きく変化した時期であった。ガンビール(皮なめしに使う植物性の薬剤)や砂糖キビ、コーヒー農園の開発、スズ採掘などの新しい産業が生まれた(それまでのスズ採掘は産業規模ではなかった)。外来資本が流入し、外来の労働者が急速に増えていった。有史以来続いた農耕社会と交易社会の二重構造が綻び始めた。マラヤ文化の灯も消えようとしていた。
その最大の動因がスズ鉱山の開発だった。イギリス海峡商人たちは、もともと危険の多い交易稼業で儲けてきたが、いまやそれだけに満足せず、マレー半島の浅い沖積土に眠るスズ鉱の開発に積極的に飛び込んでいった。名にし負うスズと銅の大鉱山を持つコーンウォールから来た彼らは、それがお金になることをよく知っていたのである。また2,3世紀前に移民してきた食うや食わずの華人・アラブ人たちの末裔が、この頃には交易商人として成熟していた。彼らもまた開発に投資した。いや、むしろ彼らこそ、本当の立役者だった。以下、スズを中心に、さらに半島の変化を追ってみよう。
◆マラッカのスズは、砂金と同じくらい古くから知られていた。少なくともAD2世紀頃までには中国やインドへ出荷されている。その後、千数百年間、交易は絶えることなく続いた。仕向け先はヨーロッパよりも中国が主で、採集法は原始的だった。その傾向はオランダが進出してからもほぼ2世紀の間変わらなかった。
スズの鉱床は、主に花崗岩に関連して存在する(ペグマタイト、堆積岩へ貫入したグライゼン、スカルンなど)。ほかの各種金属とともに岩石中に含まれているので、これを砕いて採集する。こうしたスズの(初生)塊状鉱石を山スズという。(ギャラリーNo.130)
花崗岩は比較的風化に弱い岩石で、地表の露頭は長い年月の間にボロボロに崩れ、雨水に流されて下流の河川沿いに堆積する。そのため沖積層中(漂砂鉱床)にもスズが大量に、かつ高純度で含まれていることがある。これを川スズ(または砂スズ)という。
マラッカスズの多くは、川スズだった。半島西岸の河口付近やジャングルの底を流れる河沿いには至るところに鉱床があった。産地として、古くから知られていたのは、マレー半島のペラク、セランゴール、タイのプーケット島などである。
川スズの採集は、砂金のそれに似ている。鉱物採集家には馴染みの、椀掛けと呼ばれる一種の比重選鉱法だ。浅いお椀や板子で河底の砂をすくい、流水中で静かに揺らして軽い砂を流し去る。残った比重の大きな黒い砂がスズである。マレー人たちは何世紀にも亘って、このような原始的な方法でスズを採集していた。ポルトガルやオランダが、華人労働者を使うようになると若干の技術的進歩が見られたが、採集原理は変わらない。ジャンク・セイロンと呼ばれ、モンスーンに遭遇した船の格好の避難港と目されたプーケット島では、16世紀からスズの採集が盛んになったが、後に島の風物詩となる浚渫船の登場はまだ何百年も先のことである。
マラッカのスズがヨーロッパ市場と本格的に結びつくのは19世紀に入ってからだ。この時期、欧米で缶詰めや石油缶などの需要が急激に増加したことに呼応している。その背景には、ヨーロッパ内で採れるスズだけでは膨れ上がった需要に対応しきれなかったこと、また植民地政府を含むマラッカ諸国の内情が急速なスズ鉱山開発を促したことがあった。
★ここで、コーンウォール(コーンワル)の鉱山について簡単に触れておこう。イギリスの南西部に突き出したコーンウォール半島は、マラッカ以上に古いスズの産地で、おそらくBC20世紀以前からフェニキア人(でないかもしれないが)の手で崖や川沿いの砂スズ(川スズ)が採集されたとみられている。少なくとも、シーザーの時代には、ローマまでスズが送られていた。その後、川スズの源である山スズの鉱床が発見され、本格的な鉱山として繁栄してゆく。1201年にはジョン王により、最初の「スズ憲章」(Stannary Charter)が発布された。大陸でブリキの製造が始まると、コーンウォールのスズは、重要な原料供給源となった(脚注5)。銅も豊富で、1851年にはヨーロッパの銅産の3分の1がコーンウォールとデボン地方で占められたという。19世紀のコーンウォールは世界のスズの中心地であった。最先端の蒸気機械を駆使した採掘法が発達し、その技術が世界中の鉱山で求められた。鉱山技師たちは、アメリカを始め世界に広がっていった。先走りするようだが、19世紀末、マレー半島のパハンで始まった山スズの開発に、彼らは決定的な役割を果たした。しかし同じ時期、コーンウォール自体は、採掘が地下深部に及んでコスト高となり、海外の安いスズにおされて相次いで閉山してゆくのである。マラッカとボリビアのスズが増産されると、もはやコーンウォールの出る幕はなく、1932年までにほとんどの鉱山が終焉を迎えた(29年の大恐慌がスズ不況をもたらした)。
詳しいお話は、いずれ機会があったら書くとして、ここでは、19世紀までコーンウォールはヨーロッパの(イギリスの)スズ需要を充分に賄えるだけの大鉱山だったこと、マラッカスズの開発は、コーンウォールスズとの競争下で行われたこと、コーンウォールの鉱脈は19世紀末に枯渇し始め、コストその他の理由でマラッカのスズがさらに脚光を浴びるようになったこと、その開発にコーンウォールの技術が導入されたことを指摘するにとどめよう。
★1824年の英蘭協定以後、1874年のパンコール協定まで、イギリス植民地政府は、基本的に半島の内政に干渉しなかった。利益よりもリスクが勝ったからだ。ジョホール朝は昔日の栄光すでになく、サルタンたちの内紛が続いていた(交易商人や植民地官僚たちが火種になったことも多い)。自由港シンガポールが設立されて再び交易が盛んになり、換金作物の栽培が進んだ。ヨーロッパ市場を目指して新しいスズ鉱山が開かれていった。これらの産物を運ぶ道路や鉄道が建設されていく。伝統的に生産者層を持たなかったマレー半島に、外来の労働者たちがやってきて、コロニーを作った。新しい産業と労働者は、新たな税収源であり、新しい兵力となったから、サルタンたちはこれを積極的に受け容れた。河川の通行に付随した徴税権は、土地開発権にすり替わった。新たに人頭税が設けられ、鉱山や農園単位で徴税されるようになった。その一方で、新しく作られた輸送路が、旧来の河川交通路から上がる税収と封建制度をなし崩していった。古いマラヤの国家運営システムが衰退し、新しい産業に適応した社会が生まれようとしていた。交易社会では、何の価値も生み出さなかった名目だけの領土は、いまや付加価値の源であった。サルタンたちは、しばしば、スズ鉱山や農園となるべき土地(というか貸与すべき土地)の相続を巡って争った。古いシステムが崩れ去ろうとする今、開発可能な土地の確保は、生き残りをかけた戦いでもあった。サルタンたちは税収不足に悩み、つねに戦費の確保に苦労していた。そのため、敵味方双方が同じスズ鉱区の開発権を担保に資金を調達することも珍しくなかった。鉱山開発は、投資家たちにとって、しばしば乗るかそるかの大博打だった。双方に投資する抜け目ない商人たちもいた。うまく勝ち組についたとしても、開発した鉱山が戦場になり、労働者は兵役に駆り出され、あげくサルタンの気まぐれで突然開発権をキャンセルされたりしたのでは(これもそう珍しいことではなかった)、よほどしたたかな投資家でなければやっていけなかったのも事実である。
★海峡商人たちは、植民地政府の介入を強く求めていたが、政府は刈り取りの時期を待って傍観していた。そんな中で、内陸部開発に実質的に貢献したのは、華人資本と華人労働者(苦力)たちだった。スズ鉱山の多くは、彼らの手で開発された。したたかなことでは、ひけを取らないイギリス商人たちも、当然利権に群がったが、彼らほどうまく利益をあげることができなかった。イギリス流のやり方は何かにつけ経費がかかったからだ。両者の手法を対比してみると面白い。イギリスは、機械を使ったボーリングで探鉱したが、これにはずいぶんとお金がかかった。華人たちは、マレー人の呪術師(パワン)を雇ってきて鉱床を探させた。竹竿(ダウジング・ロッド)を大地に立てて占うのだが、不思議とよくあたったという(※脚注4)。ただし、パワンたちは、地表近くの浅い鉱床しか探し出せなかった。託宣が下ると、マレー人を使ってジャングルの表土を取り除いた。剥き出しの大地を露天掘りし、簡単な土木工事で河川から水を引いて、浅い川床で転車と呼ばれる水車を回し、巧みに土を洗い流してスズを選鉱した。この作業に携わったのは、中国南方から来た華人苦力たちだった。人海戦術とはいえ、彼らのやり方は選鉱でも精鉱でも、旧来のマレー人のそれよりずっと大掛かりで効率がよかった。雲南地方の技術が導入されたものという。設備投資は、わずかで済んだ。
イギリス資本の鉱山会社も、実地作業は同じように華人に頼った。しかし、出稼ぎ労働者を組織的に鉱山に送り込み、きっちり働かせることにかけては、華人のコネクションとノウハウが勝った。彼らには郷党による一種の秘密結社の伝統があったからだ。その気になれば、華人鉱山主は、いつでも英資鉱山の操業を妨害できた。
本国から来たイギリス人監督官は高給を取ったし、労働者との仲介にはどのみち華人監督者が必要だったから、その分人件費にも差が出た。
イギリス資本の場合、土地の開発権は何度も転売を経ているのが普通だったので、イニシャルコストそのものが高かった。鉱山開発のリスクと収益を天秤にかけたイギリス商人たちは、利権を手にすると、すぐさま転売して利ざやを稼ぐ方を好んだのだ。最終的な出資者となったのは、イギリス本国に住み、余剰資金を抱えた株主たちだった。彼らはマレー半島の実情などこれっぽっちも知らなかった。一方、華人出資者は命がけで陣頭指揮をとったから、心構えがまるで違った。また、イギリス側はコーンウォールの技術がそのまま通用すると考える傾向があったが、マレー半島のスズは、この時期まだ川スズが多く、機械化した設備よりも、安い華人苦力による原始的な採集法に分があった。
結局、イギリス資本の鉱山会社も、実際の採集作業は華人へ下請けに出すのが通例となった。そんなわけで、18世紀から19世紀にかけて、内陸の開発はほとんどが華人の技術と資本と労働力で推し進められたのである(それとインド人労働者)。
★そうはいっても、鉱山の開発リスクがあまりに大きかったのは、華人資本家にとっても同じことだった。ではなぜ出資を引き受けたのか。ひとつには当たれば大きかったからだろう。しかし収益という面でより現実的な動機は、彼らにアヘンの小売権(アヘン宿の経営権)が与えられたことである。アヘンは、マレー半島開発の切り札だった。植民地政府は、出資者を惹きつけるため、進んで専売権を下付する政策をとった。下付は入札制だったが、それは名目に過ぎず、華人秘密結社は談合して入札価格をコントロールした。実質の税収と植民地開発を彼らに頼りたい政府は、しばしば補助金を与えたり、入札価格を下げるなどの要求を黙って飲んだ。政府にとっても、専売権の下付は、徴税代行システムとして有効だったし、税収の増加という点でも期待出来たからだ。
アヘン!アヘンがなければ、わずか半世紀の間にこれほど半島の開発が進むことなどなかっただろう。スズ鉱山には大勢の労働者たちが働き、ひとつの町を作っていた。19世紀半ば、セランゴール内戦に揺れた、後の首都クアラ・ルンプールは、苦力でごったがえす開拓の町だった。川をはさんで一方に鉱夫小屋、賭場、アヘン窟、売笑窟が並んでいた。この組み合わせは鉱山町の典型であった。アヘン宿は実入りのよい商売で、たとえ鉱山からの利益が上がらなくても、アヘンの収益がそれを十二分に補った。西岸の丘の上には鉱山町を見下ろすように植民地政府の官舎があった。彼ら役人の給料は事実上アヘンの収益で賄われていた。鉱山労働、納税、徴兵、渡航費や生活物資の前借り、賭場の借金など何重もの拘束を受け、そのうえアヘンの悪習に染まった苦力たちの苦労は、並たいていのものでなかった。体を張って生きる彼らにとって、状況は偉大な悪循環だった。アヘンは債務奴隷的生活の憂さを払ったが、間違いなく健康を損ねたのだから。鉱山の労働は苛酷だった。中毒が進んで働けなくなった苦力たちは小屋の中に放置され、ばたばたと死んでいった。ペラクの鉱山中心地ラルートでは、苦力の年間死亡率5割という記録が残っている。それでも、鉱山の開発は相次ぎ、スズの産量が上がり、半島は急ピッチで切り開かれていった。港湾が整備され、鉄道が敷かれ、道路が建設された。これらは、みなアヘンから上がる税収があって、初めて為し得たことだった。

★次の表は、19世紀半ばのマラヤスズ(マレー半島で採れるスズ)と、バンカスズ、コーンウォールスズのヨーロッパ市場における出荷量(トン)である。
マラヤスズ バンカスズ コーンウォールスズ
1831-35 5,086
3,935 20,905
1836-40 4,143 7,876
25,500
1841-45 4,212 12,261 32,485
1846-50 4,046 20,329
34,000
1851-55 6,499 21,034
30,524
1856-60 8,928 29,891
33,474
1861-65 16,385 22,895
46,079
1866-70 17,795 24,782
47,950
1871-75 29,257 23,775
49,988
需要の増加を受けて、この半世紀にコーンウォールのスズ生産は2.5倍に増えたが、マラッカのスズは6倍に跳ね上がった。半島側・島嶼側あわせると、1850年代には早くもコーンウォールの出荷量を凌駕している。開発がいかに急速だったかがわかるだろう(同じ時期にイギリスの食器生産量は5倍に伸びた)。ついでに言えば、1869年に開通したスエズ運河は、ヨーロッパとマラッカ間の輸送距離を3分の1に縮めた。その経済効果は計り知れないほど大きかった。安いマラッカスズがヨーロッパ市場を席巻し、コーンウォールの凋落は時間の問題であった。
急速な開発は、深刻な環境問題をはらんでいた。華人のスズ鉱山は、地表付近にある豊かな鉱脈だけを掘るものだった。ジャングルを剥いで、土砂をどんどん下流に流した。スズの品位が落ちると、鉱山を放棄して、次の鉱区に移り、同じことを繰り返した。森林は失せ、マングローブの海岸は素晴らしい速さで埋まっていった。資源を濫費する贅沢な開発だった。太古から続いた半島の景観は、この世紀に一変した。河川下流の田畑(野菜などを作っていた)では、鉱毒被害も起こり始めた。しかし、もちろん開発の手が休まることはなかった。
★19世紀末になると、さすが豊かな川スズも、簡単に掘れるところは掘り尽してしまい、いよいよ品位の低い鉱床や地下深くを掘らなければならなくなってきた。露天掘りに代わって、タルンという竪坑掘りが始まった。しかし採掘できる深さはせいぜい3メートルで、地底のスズ砂を運び上げるのに多くの人間が必要だった。人力に頼る華人方式は、コストがかさみ、効率が落ちた。折から、過酷な労働条件が問題となり、苦力の待遇改善が進んでいた。アヘン戦争以後、同胞意識が目覚めたのか、アヘン忌避の風潮が高まり、そちらからの収入も見込めなくなってきた(労働者たちが悪習を放棄したというより、経営者側が、労働意欲を失わせるアヘンを禁止して、もっとよく働かそうと思ったのである)。
採掘はより内陸部へ進んだ。半島東部のパハンが脚光を浴び始めたのはこの時期である。1890年代、ロンドンではパハンスズの投機ブームが起こり、100を超える鉱山会社が名乗りをあげたが、これらの鉱山は、山スズを掘るものであり、従来の採集法は役に立たなかった。今こそ、コーンウォール流の科学的探鉱、採掘法が必要であった。
こうして鉱山開発は、機械化の時代を迎えた。一方、刈り入れ時とみた植民地政府が、手のひらを返したように内政に介入し始めた。彼らは法律を盾に、休止状態の華人鉱区をどんどん没収していった(1890年頃はスズ不況だった)。1906年に最初の蒸気ポンプが導入された。1910年、世界はスズ景気に沸いた。浚渫船が導入されたのは1912年だった。鉱山は近代化を遂げた。そうなると、株式によって巨大な資金を調達出来る欧米資本が断然有利である。1910年頃、欧米資本と華人資本鉱山のスズ生産比は、1:4の割合だったが、1920年は、1:2くらいになった。1929年にはついに比率が逆転した。(華人資本は、次第にゴム園の開発に移っていった。)
一方、1920年にタイ−シンガポール鉄道が開通し、半島の輸送網が完成したことによって、マラヤ伝統の河川封建制は完全にとどめを刺された。こうしてマレー半島は華人商人と欧米資本の支配するイギリス植民地として大発展を遂げたのだった。単なる中継交易地点だった半島は、いまや世界の生産拠点としても重要な存在となった。
◆1930年代のスズ不況や二次大戦後の好況を迎えながら、マラッカのスズは世界に供給された。戦後、マラッカ植民地は、マラヤ連邦(後にマレーシア)、及び(統一)インドネシアとして独立したが、産業はそのまま引継がれた。スズは経済発展の原動力であった。現在のマレーシアで見られるどの道路も都市も、スズとゴム(20世紀以降盛んになった)とに関係せず建設されたものはないという。
しかし、20世紀の終り、200年に亘って半島の発展を引っ張ってきたスズ産業は、ふいにその幕を閉じる。マレーシアのスズ生産は、1972年にピークを迎え、年産77000トンを記録した。が、1985年に相場が暴落すると、一転して衰退に向かった。壊滅したといってもよい。1996年の産出量は5000トン。往時の15分の1以下である。850ヶ所あった鉱山は、35ヶ所に減った。多くのスズ企業は、それまでの豊富な資本蓄積とマレーシア経済の発展の中で、積極的に他事業へ転換していった。最大手のマレーシアマイニング社は、建設業や自動車部品製造など幅広い分野に事業展開し、鉱業部門の売上は今では数%を占めるに過ぎない。かろうじて残ったスズ鉱山も、折からの建設ラッシュで建設用砂の需要が急増したため、砂を主産物に、スズを副産物にというスタイルにシフトした。
ロイヤル・セランゴールといえば、マレーシア名産の有名なスズ製品ブランドだが、某大手商社の部長が耳うちするに、原料のスズはマレーシア産ではないという。その姿が過去の栄光と現在の状況を問わず語っているといえようか。
なお、インドネシアは、現在も年産5万トンをあげ、中国と並ぶスズ鉱石の世界的産地として、その地位を保っている。
★かくて祭りの後となったマレー半島の山地は、今では剥き出しの鉱山跡だらけである。スズを掘った廃鉱が、いたるところに傷あとのように残っているという。熱帯のジャングルの土壌層は脆弱で、一度切り拓かれると100年やそこらでは原状回復しないのだ。そのため洪水の後の荒地のような、草木一本生えない風景が広がっている。また、スズ採集が原因で土壌が汚染され、緑が回復しない土地もある。この点については、次のテキストを参照していただきたい。タイのスズ鉱山についての報告だが、事情はマレーシアでも似たりよったりである。また、本文で触れなかった浚渫船によるスズ採集の様子も分かるだろう。スズ鉱山跡の水質汚染について。
鉱山跡地の汚染は、タイでもマレーシアでもインドネシアでも、深刻な問題となっている。プーケット島では、露天掘りをした後には草木が生えず、雨水が溜まって池になっていることが多いという。ガイドの方に、その水は飲んでも大丈夫ですか、と聞いたら、駄目だと言って笑った。雨季に池があふれて、畑に流れたりすると、作物がすっかりやられてしまうという。しかし、人間はなかなかしたたかな生き物で、海岸沿いにある鉱山跡のラグーンは、リゾートホテルに取り込まれて、美しい景観を提供し、観光客を喜ばせている様子だ(プーケット島は、スズ産業が崩壊して以来、13年ほど前から観光産業にシフトし、今ではアジア有数のリゾート地と目されている。パトンビーチの夜の賑わいは、心が浮き立たずにおれない。)
★スズの産出が減ったため、鉱業分野では相対的に銅や金の生産が目立つようになった。95年には銅がスズの産量を上回っている。古くから知られていた金については、オランダ植民地時代まで砂金が重要な輸出品だったが、近年はむしろ山金と呼ばれる鉱石からの採集が主体となっている。特にここ数年、半島東部のパハン州にあるペンジョム鉱山の開発が著しい。95年のマレーシアの産金高は3トン程度で、その半分が、ボルネオ島のマムート鉱山のものだった。しかし、96年12月にペンジョム鉱山で生産が始まると、産金高は一気に倍増し、98年にはさらに40%増加したという。黄金半島の名も、まだまだ昔語りではない。
ただ、スズの廃鉱汚染とは別の面で、金鉱山にも公害問題が発生している。鉱石から金を抽出するのに、アマルガム法を採用しているのだが、作業に従事する女性たちは、素手で水銀に触れているという。水銀中毒患者が増え、奇形児が生まれているらしい。なんてことをするのか。
もっとも、東南アジアにおける劣悪な労働環境、有毒廃棄物質の垂れ流し、環境汚染といった問題は、ひとり鉱山に限ったことではなく、あらゆる生産分野で横行しているのが実態である。
◆最後に、マレーシア政府が標榜している「ブミプトラ」という一種の人種優遇政策に触れて、このページを終りにしよう。
これまで述べてきたように、19世紀以降の半島開発は、外来の華人やインド人たちが担い手だった。もともと半島に住んでいた原住マレー人(ブミ)は、昔からの農業や漁業を続け、新しい植民地産業からは間接的な恩恵を受けるに留まった。
★1920年以来、イギリスは政治的圧力と外交手腕を駆使して、マレー半島をほぼ完全に掌握した。その支配下で、前世紀からの産業構造に基づく民族別分業体制が確立した。経済を支配するのはイギリス人、マレー系(ブミ)は伝統農業、中国系(華人)は中小規模の工業や商業・流通、インド系はゴム園や鉄道・建設業に従事するという役割分担が定着したのである。そして、華人移民と原住マレー人との間に経済格差が生まれた。市場経済が発達するほど、一次産業とニ次、三次産業との間で所得格差が開いたからだ。
この体制は、2次大戦後、民族意識の高揚によって独立した「マラヤ連邦」(マレーシアの前身)にそのまま引き継がれた。ただし支配者だったイギリス人が去ったため、裕福な華人に対するマレー人の不満が一挙に表面化することとなった。マラヤ連邦は、マレー人の国家(イスラム最高指導者であるサルタンたちが治める各州の連邦で、互選により、国の象徴たる国王を選出する)として独立したが、国の経済を握っていたのは華人移民たちだった。マラヤ民衆からすれば、ここは誰の国なのか、ということになる。1969年には、彼らの危機意識が頂点に達し、大規模な人種暴動が起こった。経済格差の是正が国家の緊急課題となった。
★少し横道に逸れるようだが、現在、マレーシアの住民は、2300万人。その59%がマレー系(マレー人・ブミ)、25%が中国系(華人)、7%がインド系という構成だ。中国系住民は、たいてい3〜4世代前に移民してきた華人労働者の子孫である。初期の移民者たちは、本国を食い詰めて出てきた者が多く、勤勉で、マレー人より安価な賃金でよく働いた。また向上心があった。彼らは世代を追うごとに財産を増やし、社会的地位を向上させていった。初代はスズ鉱山やゴム園の労働者。貯めた資金を元手に2代目が商売を始める。その子供(3代目)が高等教育を受けて企業投資家や学者(医者・弁護士)として成功する。これが、典型的な華人のサクセスストーリーである。一方、マレー人は、もともと生活に困っていたわけではなく、自然のもたらす豊かな物産の中で暮らしてきた。産業が発達すると市場経済を視野に入れた農作物栽培や海産物の採集を行い、資本主義にも多少は馴染んできた。しかし、依然蓄財の意識が薄かったし、商売に投資する者も少なかった。華人とマレー人との性格の違いだろうか。何百年もの間、略奪を受けてきた原住民の本能だという説もある。ともあれ、両者の間に貧富の差が生じたのは、民族的な現象であった。(ちなみに、その昔スマトラ島のミナンカバウ人は商才に長け、半島のマレー人に恐れられていた。植民地時代以降は、華人が、その商才で恐れられた。どうもマレー人種は、生来、商売気に乏しいのかもしれない。)
★さて、ブミプトラは、そうした深刻な経済格差を背景に打ち出された政策だった。マレー人(ブミ)の華人に対する不満を抑え、一方華人の実質的な経済能力をも温存しようという巧妙な意図が盛り込まれていた。雇用構造の再編と民族間の所有資本の再編、マレー人が経営する企業の育成、それらによる所得不均衡の是正が掲げられた。具体的には、まず民族構成比に応じた雇用が義務づけられた。例えばマレー系が人口の6割を占めるとすれば、企業は、マレー人を全就労者の6割以上雇用しなければならない。また外来労働者の移入も制限された。企業が外国人を雇うには、政府の許可が必要になった。さらにマレー系企業に対するさまざまな優遇施策が採られた。
これでは、マレー人以外の民族の抑圧だと思われるかもしれない。実際、マレー人は特に優秀でなくても採用されるのに、華人はいくら優秀でも希望の仕事につけないといった問題も生じている。
ただ、ある方の表現を借りれば、ブミプトラは「マレー人にゲタを履かせる」政策であり、そうしてやっと、華人と対等に競争できるという、苦肉の策だったのである。政府の見解も、まさにそこに力点がおかれていた。
ある大臣は、「残念ながら、マレー人は、自ら劣等民族であることを認めなければならない。優遇措置の下で徐々に進歩してゆく機会を与えられなければ、我々は滅びるほかない。」と言ったそうだ。
商社の方にこのお話を伺った時、「国民に向かって、私たちは劣っていると公言できるところがすごい」と感想を述べられた。確かに、そんなことを言って、次の選挙を乗り切れる政治家は日本にはいないだろう。
しかし、一歩へりくだってでも実質的な優遇を勝ち取り、しかも華人のご機嫌(=経済力)を損なうことなく国を発展させていこうとする姿勢には、古くから交易社会で生きてきたマレー人の知恵が結晶しているとも言えるだろう。実際、この政策によって、華人資本が国外に流出して、国庫が破綻するといった事態は起こらず、むしろ急速に経済発展の道を歩んでいったのだから。植民地時代、イギリス政府がマレー人よりも華人に税収と半島の開発を期待したことはすでに述べたが、現代のマレーシアでも、同様の懐柔政策が巧を奏したとみるべきだろう。
★ブミプトラ政策の甲斐あって、今のマレーシアは、マレー人が働きたいと思えば(あまり思ってないという説もある)、必ず雇用がある状況になっている。また、民族間の資本所有比率は、1990年の段階で、ブミ20%、華人46%、外資系25%となった。将来的にはブミのシェア30%を目指しているが、真に競争力のある企業を育成するという建前により、政治的圧力はかけられていない。かつてスズやゴムといった一次産品の輸出に頼っていた経済は、工業製品の輸出に変わってきた(ボルネオ島では石油が採れて、重要な収入源になっている)。2020年までに先進国入りを目指す、「ワワサン2020」計画が進行中で、クアラ・ルンプールとその郊外にある国際空港の間の広大な土地に、新しい巨大ハイテク都市サイバージャヤが建設されつつある。内陸開発を支えたスズ産業の衰退とともに古い植民地時代の影が薄れゆく一方、人種バランスの取れた新しい国作りが力強く推進されているのである。
− 了 −
2001.7.12 SPS
追記:随分久しぶりにクアラルンプールを訪れる機会があった。前の時のことはもうあまり覚えていないので比較は難しいが、市の中心地域は高層ビルの林立する現代都市の景観を呈していた。ショッピング・モールは巨大で、上海やバンコクにも共通する「新興アジア」的なオシャレな大都会の感じがした。超高層ビルとして有名なランドマーク、ペトロナス・ツイン・タワー(452m)を上回る高層タワービルが建設中なのが印象的だった。しかも2つ。
一方で昔ながらのチャイナタウンや迷路的な場所も残っている。
モノレールなどの公共鉄道網が整備され、便数も多くて移動が随分便利だった。しかしスマートフォン経由の配車サービス Grab の便利さは凄まじく、これを利用出来る環境ならピンポイント移動がかなり楽である。(従来のタクシーサービスは Grab のために壊滅的らしく、滞在中 grab の配車で普通のタクシー車が来たこともあった。)
「ワワサン2020」は、1991年にこの展望を示した4代首相のマハティール(1925- )が 2003年まで 22年間の長期政権を務めた後、首相交代による政策変更もあり、2020年の目標達成は困難な状況とみられる。マハティールは 2018年に野党の立場から政権を取って再び首相(7代)に就任したが、2025年までに財政を健全化して先進国入りを目指せる、としている。ブミプトラ政策はさまざまな矛盾や批判をはらみながらも、なお維持されている。サイバージャヤは新興都市で、依然としてまだこれからの観がある。
マレー錫の採掘は現在では昔語りとなったが、統計を見るとインドネシア産の粗錫の精錬にはマレーシア企業が一定の役割を果たしている。世界的には中国、インドネシアが2大生産国で、ペルーやボリビア、オーストラリア等が続く。近年ミャンマー産(マンモー鉱山産)の錫鉱が中国資本の投資・開発によって大量に(乱)採掘されてきたが、急激に産量を落とした。枯渇が近づいたと言われる。
(2019.8.30)
このページは、マレー半島、プーケット島などを訪問した折に、スズについて興味を持った、その覚書きみたいなものです。インターネットを含め、いくつかの資料を参考にしましたが、マラッカの歴史等に関するメインソースは、鶴見良行著「マラッカ物語」(時事通信社、1981)に依ります。読み下すのに少々骨の折れる本ですが、マラッカ史に興味のある方にはご一読をお勧めします。
※脚注1:スズの鉱石は、事実上、錫石(二酸化スズ)だけだといってよい。自然環境下では安定度の高い(化学反応しにくい)物質だが、比較的簡単な方法で精錬可能である。木炭(粉末)と砂スズを混ぜて、炉中で5〜10時間加熱すると、1000〜1200℃くらいの温度で反応が進み、酸化スズが還元されて(金属)スズとなる。この技術は、鉄鉱石(酸化鉄)を初め、酸化状態で産出する各種の金属を還元するための基本的な手法である。古代の金属精錬は、おそらく木炭の火による金属の「浄化」から始まったのだろう。
融点が300℃以下なので、還元されたスズは溶融している。その中にはさまざまな(金属)不純物が含まれているが、湯温の低下とともに融点の高いものからスラグ化するので、順次除去してゆく。こうして粗スズがえられる。フラックスとして石灰や珪酸ソーダを加えることもある。この場合は、酸化スズの一部もスラグに入るので、再度抽出しなくてはならない。粗スズは、まだ若干の不純物を含んでいるため、溶融スズを滝のように流し落としたり、生木をくべて発生するガスと反応させたりして、純度を高める。 (戻る)
※脚注2:スズは衛生的に無害で、また有機酸にほとんど冒されないため、古くから生活用器、特に食器として重要な金属だった。ピューターのようにスズを50%以上含む食器(酒杯など)は昔から人気がある。スズには水を浄化し、毒を中和する働きがあるとされている。スズは両性元素で、(強い)酸にもアルカリにも反応して安定化合物を作るからだろう。中国のある地方では、井戸の底にスズの板を沈めておく風習があった。湧水を澄ませるためである。水を汲んでは濁りを取り、酒壺にしては酒の味をまろやかに、ビールジョッキに用いるとキメの細かい泡がたって旨みが増すという。スズ自体が水やお酒に溶けて旨みの元となるのかどうか知らないが、おそらく健康にもいいのだろう。人体にも微量含まれており、日常の食生活でごく微量ずつ摂取されている。ネズミにとっては生体必須元素である。
なお、李時珍「本草綱目」の錫の項に、「錫は太陰の気を受けて生ずる。その気は200年動かずして砒となり、砒が200年経った時始めて錫が生じる」と土宿本草の説を紹介している。錫は砒から変化したものというのだ。また錫が200年動かずに太陽の気にあうと銀になるという。
「今世人は酒を新しい錫器の中に入れ、そのまま久しい間浸漬しておいたものを人を殺す毒とする。それは砒から錫に化成して間もないうちに採取したものはその中にまだ毒が含まれているからだ」と書いている。当時は純度の高い錫を得るのが難しく、砒素が混じっていたのかもしれない。
早くから陶器が普及した中国や日本と違い、近世以降の欧米では庶民の食器はたいていブリキ製(またはピューター製)だった。金・銀食器や陶磁器を使ったのは一部の王侯貴族たちだけである。
ちなみに現在ブリキは、缶詰のほか、歯磨き粉のチューブ、スプレー缶などにも使われている。タバコの包み紙に使われていたこともある。アンデルセン童話の「鉛の兵隊」は、本当はスズ(とアンチモニー)で出来ていた。近年の翻訳本には原語通り、スズの兵隊と訳されているが、ある年齢層の方なら、「鉛の兵隊は、雪の女王の家来♪」というアニソン(テレまん)のフレーズをご記憶だろう。スズを鋳込んだり、ブリキを接合した玩具は、プラスチックが取って代わる30年ほど前まで定番アイテムであり、今では好事家の郷愁を誘っている。なお建材としては、亜鉛メッキ鋼板、つまりトタン板が圧倒的に好まれている(キズがついても鉄が腐食されにくい)。
ピューターには主に3つの種類があった。約1%の銅を含む「ファイン」、約4%の鉛を含む「トリフル」、約15%の鉛を含む「レイ」である。鉛の有毒性が公知となった現在は、鉛を含まないピューターが用いられている。 (戻る)
※脚注3:学者さんの中には、シナイ半島には青銅を含む鉱石があり、エジプト人は、まず青銅を知ってから、銅の精錬に気づいたと仰る方もある。銅鉱石から純粋の銅を取り出すには高度な技術が必要で、むしろスズの混在した青銅の方が抽出しやすいのだという。シナイ半島の鉱床は、コーンウォール、あるいは日本でいえば兵庫県の生野や明延のように銅やスズその他の金属を豊富に含んでいたのであろう。それで質のよい青銅が採れるならこんな簡単なことはない。しかし、銅鉱石より先に自然銅に気づいたという可能性も否定できないだろう。むしろ、自然銅を知り(あるいは孔雀石からの還元法に気づき)、精錬の容易な砂スズを知り、その後、スズを溶かした溶液中に銅を投入して、青銅を知ったと考える方がすっきりしているように思える。こうすると純粋の銅より低い温度で鉱石が溶け出し、青銅が得られるからだ。
なお、「鉄の歴史」の著者ベック博士は、銅、スズの両鉱石から青銅を直接製造することはまったく不可能だと断言している。
余談にわたるが、プリニウスの博物誌巻7-56[195]以下に次の記述がある。
「銅の採掘は(アグリオパの息子キニュラによって)キプロス島でなされた」「アリストテレスはスキタイ人のリュドスが銅を溶かして細工をする方法を教えたと考えたが、テオフラストスは、それはフリュギア人のデラスであったと主張する。青銅の製法は、ある人々はカリベス族に、ほかの人びとはキュクロペス人に帰している。鍛鉄法は、ヘシオドスはクレタ島にいたイダのダクティリ族と呼ばれる人びとに帰している。アテナイのエリクトニオス、あるいはほかの人びとによればアイアコスが銀を発見した。金の採掘と精錬はパンガエウス山でフェニキア人のカドモスによって、あるいはほかの者によれば、パンカイアのトアスあるいはアイアコスによって、あるいはオケアヌスの息子のソール(太陽神)によって発見された。このソールにまたゲリウスは鉱物からとった薬の発見を帰している。スズはミダクリトスによってカッシテリス島から初めてもたらされた。製鉄法はキクロペス族によって(発明された)」
昔のギリシャ人はカッシリテス(カッシリデス)は、イスパニアからブリタニア南部海域のどこかにある島か半島であると考えていた。BC1Cのディオドロス・シクロスはカッシリテスがコーンウォールだと正しく認識していたという(神代地誌)。古代ギリシャに錫はカッシテロスと呼ばれ、錫石(カシテライト
Cassiterite)の名はこれに因んでいる。 (戻る)
※脚注4:エリアーデの指摘するところを述べれば、「マラヤの鉱夫はスズとその性質について特別な観念を持っている。スズは、鎮めておかなければならない、ある精霊の支配と保護の下にあり、また、それ自体に生命があると信じられている。スズは、ある場所から別の場所へ移動することが出来るし、特定の人々やモノに共感(あるいは親近感)を示すことがある。逆に忌避の念を持つこともある。従って、鉱夫は、スズ鉱石に対し一定の敬意を払うことを要求されている。奇妙なことではあるが、何も知らなくてもスズ鉱は採集出来る。しかしそういうやり方で鉱山開発を進めることが絶対に必要だと信じられているのだ。」(A.ヘイル)
鉱石の動物的挙動を見過ごしてはならない。鉱石は生きており、意思のままに動き、隠れ、狩り立てられる鳥や獣が狩人に示すのと同じ挙動(共感や反感)を示すのである。マレーにはイスラム教が強く浸透しているけれども、この「異国の」宗教は採鉱作業の成功を確保しようと努力する場合には、無力であることを証明した。というのも、鉱山を見張り、鉱石を統御しているのは土地の古い神々だからだ。従って、旧来の宗教の祭司、イスラムによって地位を剥奪された祭司に頼ることが絶対的に必要なのだ。採鉱の儀式を司るための訴えが、マレー人のパワンに、ときには最古の原住民のひとりであるサカイ人のシャーマンにさえも呼びかけられる。彼ら呪術師たちは、最古の宗教的伝統の貯蔵庫であるがゆえに、鉱石の守護神を鎮め、鉱山に跳梁する精霊を用心深くあしらうことが出来るのである。
そういうわけで、優秀な技術を持った華人といえども、鉱山の開発はマレー人に依存せざるを得なかったのだ。 (戻る)
※脚注5:17世紀の人物で、国民経済学の創始者と呼ばれる、アンドリュー・ヤラントンは、当時、オランダを通じてドイツやベルギーから鉄製品を大量に輸入していた現状を嘆き、「イギリスが大量のスズをザクセンに輸出し、そこで製造されたブリキを輸入する不合理」をやめて、イギリスの鉄とスズとでブリキを製造することを説き、自らザクセンに赴いてブリキ製造の技術を学び取った。すぐには成功できなかったが、イギリスでブリキ産業が栄える端緒を開いた。
(戻る)