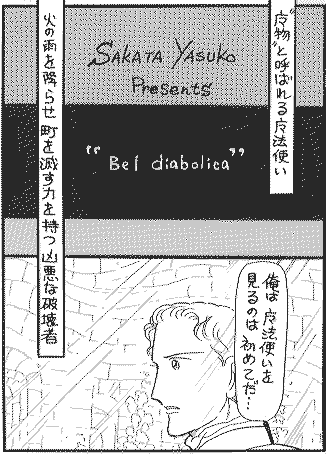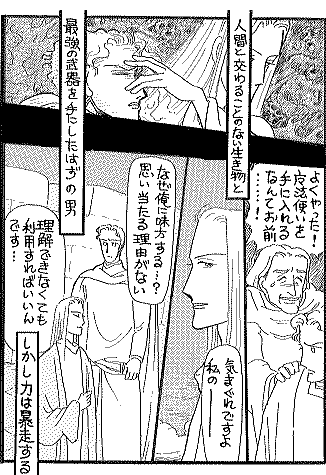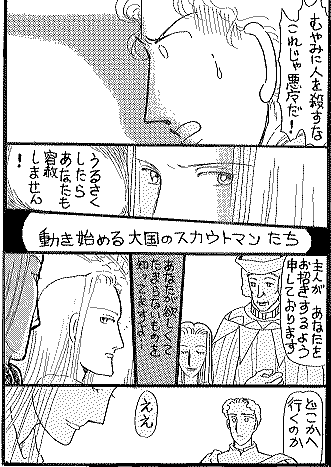僕が年来のファンを自任する坂田靖子女史(昔は女性の敬称として氏や先生に等しいニュアンスで女史を使った)の作品、「ベル・デアボリカ」が完結を迎えた。単行本第3巻が8月に上梓され、今月7日に4巻が出た。終章、小国の若き王ツヴァスと魔法使いヴァルカナルそれぞれの信条表明に接して感無量の思いに浸っている。
女史のお許しをいただいたわけではないので控えめにだが、長い待機期間をつきあってきた一読者として、ファンからみたその間の成り行きを文字にしておきたい。
ベル・デアボリカの最初の印刷物が配布されたのは、随分昔のことである。実感として10年は経っていると思ったが、ファンサイトであり坂田作品の旗艦データベースである「居酒屋はねうさぎ」を見ると、製本された私家版Sect1が出たのは 2000年4月であったという(以下、僕はこのテキストを記憶に拠って書くので、間違った情報が含まれるかもしれない)。(補記1)
その少し前、女史は魔法使いのお話を書きたい情熱にふいに満たされた。作家の創造力は、しばしばそうなのだろうが、本人の意識的な心の中にどこからともなく滲み出してきて、いつの間にか全官能を支配するものらしい。一時頭の中はそのことだけに占められて、ともかく魔法使いにカタチを持たせないではニッチもサッチもドッチもどうにもいかなくなった。ドーパミンでまくり、好きだ〜の高揚精神充溢し、やるっきゃないと掛け声言上げして、とるものもとりあえず、Sect1を短期間で描き上げられた。
もともと女史はパソコン通信とかPRG(ロールプレイングゲーム)とかにハマっていた時期があり、その関連のエッセイも出ている。いわゆるファンタジー世界はある意味生活の一部であり、慣れ親しんだ世界であった。ノンシャランな(この言葉は、お気楽とか、脳天気とか、のんのんずいずいとか、テイク・イット・イージーとか、そのテのニュアンスを現す表現として、かつて使われていた。久生十蘭あたりの世代も使ったし、70−80年代の坂田作品を評して使われたこともある)、RPG感覚竜退治アドベンチャー作品もいくつか描いている。
しかしその時現れた魔法使いのイメージは、ゲームの舞台回しとして機能するだけの表相的にふるまうステレオタイプではなかったようで、想像だが女史にとってもっと切迫した、存在のあり方、あるいは生き方を指し示す魔法使い像であったらしい。そしてその様式は、女史の土壌の一つである男同士の友情というカタチで照明されていた(もっともヴァルカナルに性別の意味があるかどうかは不明)。
ある架空世界で小さな国を継いだ、胆力決断力をそなえた誠実な青年王と、人外の「マモノ」である魔法使いの出合いによって作品「ベル・デアボリカ」は語り始められた。
このお話は、登場人物が基本的に男だけで、ごく大雑把に言ってしまえば男二人の世界である。ストーリーは政治的・権力闘争的なモチーフを動因として展開し、テーマは内省的または倫理学的である。女史自身の観方では、いたって「地味」で「商業向けではない」ように見えた。
ファンからすると、そんな物語も実際には女史の過去の作品群からそれほど外れてはいない。が彼女はこの作品をその時点で自分の描きたいように描く必要があると感じ、商業作品としては成立しない(妥協できない)と判断して自主刊行の道を選ばれた。
ちなみに女史は職業作家となってからも長く同人活動を続け、描いて世に示すほかにないが(そうしなければ創造力は滞ってしまうのだろう)、商業誌向けの味付けが難しい作品を少数の人に向けて発表する場としていた。だがそれも10数年前までのことで、再び自主制作を始めるにはかなり自分にハッパをかける必要があったらしい。ちょうど一人で国を背負ったツヴァスのように。
自刷り仮綴じの、最初のSect1が何部出たとか、どう配布されたとか、僕はもちろん知らないが、女史はたとえ一人でも二人でも読んでくれる読者があったら、それで創作は成立している、との考えを持っておられた(多分今も)。その種の創作は、もちろん描かずにいられないから描かれるのだが、受け手もまた絶対に必要とされている。作品は虚空に向けて発せられそのまま消えてゆく瞬間的な音ではなく、誰かに伝わって糧となるべき声であり、世の表の他者に必ず届けなければならない種をはらんでいるのだ。
Sect1にはそんな女史の心境を綴ったメッセージが添えられていた。非常にハイな、創作の喜びにあふれた、さあまた始めるぞ、といった心意気が、だからその時の読者みなに日の輝きのように伝わった、と僕は信じている。
ほどなく製本された私家版Sect1が配布された。これが冒頭に述べた
2000年4月発行の版だ。この本にはSect2が一緒に綴じられ、Sect1とSect2の間に「虎丸のページ」が挟まれていた。ツヴァスが魔力を封じる塔にヴァルカナルを捕らえた直後の、2人のファーストコンタクトの成り行きを友人の作家(虎丸女史)が彼女の流儀で描いたコラボ作品である。坂田女史は執筆を依頼したとき、内容についての示唆やお願いは一切しなかった。いや、ひとつだけ。好きなことを遠慮なく描いてほしいと願った。
そういうお遊びというか茶目っ気なノリは、本気を出すこと、創造の混沌、好きだ〜パワー全開の精神によって成立し、熱狂に感染した読者もまたその面白がりを共有した。
それから(データベースによれば)2ケ月と経たない間に、坂田女史が描いた部分(Sect1+Sect2)だけで再構成したベルデアボリカ1が出た。どういう経緯だったかよく覚えていないので半分想像を交えて書くが、私家版Sect1 がファンに好意的に迎えられ、作品を読みたいという反響が予想以上に大きく広がり、女史が個人的にマネージできる範囲を超えてしまったのだったと思う。悩んだ末、結論として同人誌委託販売のルートに載せたベルデアボリカ1が出された。
こうしてかなりの勢いで描き始められたデアボリカは、ところがこの後一転してペースが落ちてしまう。頭の中にはすでに作品全体が見えており、ラフもできている、と女史は表明していた。そもそも最後のシーンのやり取りがまず頭に浮かんでいたという、彼女には珍しい作品なのだったが、筆入れの時間がどうにもとれなくなったらしい。
その事情を一読者が詮索するのは分を越えていようが、現実的な生活レベルでの経緯はさておき、作家としての本能的な感覚の中に、このまま、すでに見えているだけのカタチで物語を完結させてしまうことに対する危惧があったのではないかと、最終巻(4巻)を読んだ今では思われる。
あるいは結末に至る道筋が希望していたほど見えてこなかったのかもしれない。彼女の創作作法では、ストーリーはふつう最初から見えているのでなく、描いていく中で、いわばダンジョンにあって手元の明りが行く手の道を照らし出すように、少しずつ見つかるものとしてある−女史は作品を描き出すとき、そのお話がどう続くのか知らない。だから全体が見えているといっても、実際は細部の繋がりがまだ隠れているはず、と思っていたのではないか。
いずれにせよ当時、ただ待つの身の読者は、なかなか出ない続編にひたすらヤキモキするばかりだった。
明けて 2001年2月付でベルデアボリカ2 先行発行版が委託販売ルートで発売された。Sect3を収めたこの本は、しかしその名の通り先行版とされており、少しでも早く続きが読みたい人のためにと、(女史自身なかなか続きが描けない中で自分にプレッシャーをかける意図もあって)出されたものだった。正式版は近い将来、ベルデアボリカ3と同時に必ず出す、と宣言されたので、ここは我慢のしどころと思って手を出さなかった。失敗であった。待てど暮らせど3は出ない。この頃はホームページ(サカタBOX)も完全に更新が滞っており、読者のヤキモキは心配に変わっていった。
このお話に対する女史の思い入れはかなりのものがあった。ツヴァスの宮廷での営みや人々の服装、食べ物、国々の様子など、本編とは別にこまごまとした諸事を説明するカットをいくつも描かれて、折々に配布されていた。世界をリアルなものとして掴もうとされていたのである。しかし本編に手をつけることは出来なかったらしい。時期は覚えていないのだが、ある時点で仮綴じのSect4が届いた。早期の続編刊行を断念したためだという。
(僕はSect 3を読んでなかったので、繋がりが分からずかなり悔しかった)
それから何年も経ってホームページの更新が再開されると、しばらくして嬉しい便りがファンに届いた。朝日新聞出版が興味を示し、「夢幻館」への掲載が決まったというのだ。2009年4月、ベルデアボリカは商業ルートに載って雑誌掲載された。
ところがそれも束の間、夏には「夢幻館」の休刊が決まる。ベルデアボリカは秋以降、ウェブ誌「H&F倶楽部」に隔月連載されて継続する運びとなった。女史はむしろその流れを歓迎していたようだ。もともと−坂田靖子の名を知らない人も含めて−出来るだけ多くの人の目に作品が触れることを望んでいたからだ。無料で閲覧できるWeb誌はその機会を提供してくれると期待していた。
僕はソフトの絡みがあって閲覧できなかったが(実は女史自身も閲覧出来ない環境だとか)、商業版の単行本が2010年6月に出た時にゲットした。2巻は2011年3月に出た。そして今年の夏、3巻と4巻が続けて出て、ようやく完結した。
こういう経緯を見てきたことから、デアボリカは坂田靖子にとってかなり大切な作品だったのではないかと思わずにいられない。4巻のクライマックスは素晴らしい。サカタ作品には珍しいくらい長い心情の吐露が交される。それはほとんど世界の成り立ちと自分という存在との繋がり方を、互いの存在を通して確認しあうに等しい儀式と思われる。
僕にはヴァルカナルと彼の魔法の才能が、女史と女史の創作の才能に重なってみえた。
クライマックスを迎えるまでの物語の質には不満が残る。僕は女史もそうなのではないかと思っている。描けたらいいのにと願ったようには描けなかったのではないか。もともと練りに練った構成の伽藍建築的な長編を描く方ではないし、この作品では描き上げた後に全体を見直すといった作業も不可能だったろう。
熱情に流されるように筆をとった最初の幸福な時間は途切れて長いブランクがあった。ともかくも最後まで描きたい思いで、商業誌への「仕事」として筆を執り直した。しかし、着想の頃から見えていた結末に辿りつくための活力と暗い長い道はどこかで見失われ、女史は筋運びに迷ってしまったのではないか。もちろん作者がどう思っているかは読者には本来的にまったく分からないことであるが。
繰り返すと、僕としてはこの作品の物語性は脆弱だと思う。それでも4巻のクライマックスを読むために作品全体を読む値打ちがある。そこに作者の深い肉声が籠っているように思われる。
以上、ベル・デアボリカ (Bel Diabolica)について。
バンコクにいる。休日でヒマを余しているので、朝、思い立って一日かけてこれを書いた。書いた直接の動機は、一昨日から村上春樹のインタビュー集「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」を少しずつ読んでいて、氏の言葉にいろいろなことがインスパイアされるからである。
この本を読むと、なぜ村上春樹に、僕の好きなエリアーデやディーネセン、ル・グインといった作家と同じ手応えを感じるのか分かるような気がする。彼は夢の言語を日本語に翻訳する。
村上氏の小説の書き方は坂田靖子の漫画の描き方に似ている。それでベル・デアボリカについて書かないといけないという気になった。
上述の「暗い長い道」という考えは、もちろんこの本に影響されて口をついた。村上氏は創作のとき暗闇に降りて適切な何かを拾い上げて帰ってくることが自分には出来るという。
その言葉は次のような心象風景を喚起する。
僕の好きなマキリップの「イルスの竪琴」。イムリスの風の平原の古代都市の廃墟で、アストリン・イムリスが日ごと大地を掘ってなにかの古いカケラを拾い集めている姿。
エンデの「はてしない物語」。自分を失った主人公の少年が、ヨルノミンロウドに降って、夢のカケラを掘っているエピソード。
村上春樹の「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」。世界の終わりの場所で、主人公が一角獣の頭蓋骨に保存された懐かしい記憶を一心になぞっている姿。
それは心の深みを掘ることである、と言いたい。
坂田女史、もう一度、ケルウォースの世界を掘りませんか。ベル・デアボリカにはまだ表現すべきものが隠れている気がするのです。
cf. サカタ・マンガ 覚え書き 覚え書き2 覚え書き3
補記1:実際、Sakata Box の50000hit記念画像(2000.2.24)は、ヴァルカナルのイラストである。⇒宝物0
補記2:「私(作者本人)以外の方が、どんなにたくさん解説や解釈を書いて下さってもいいし、(というよりも 大歓
迎 なのですが)、「これはこうだろう!」「それは違う!こんな話だった」 とかいろいろいって頂けたりすると、もう非常に嬉しいんでありますが、私自身が 「このマンガはこういうテーマで、こういうものを目指して、こんなつもりで書きました」 と書いてしまうと 「作者本人がこうだと言ってるんだから、
正解はこれでしょう! 他はまちがいだよ」 というふうなフンイキになっちゃって、楽しみの幅がぐっと狭まっちゃうのであります。
(というよりも、もうマンガを読む楽しみが死んじゃってます。 「私はコレのここんとこがたまらないんだっ」 というのがみつかるからいいんであって、「そうか、こう
読まないといけなかったのか・・・ふーん」 て思いながら読むのなんか、どうにも不自由というか、ナサケナイのであります。)
マンガの「原稿」というのは作者が描いて作者のものですが、マンガの「内容」や「印象」というのは読んだ人の中に浮かんだ、読んだ人の所有物であって、作者が口を出すことじゃない・・・ というのが、私の「マンガ」についての考え方なのであります。」 (坂田靖子 SAKATA
BOX /Spy the Desk 2000.3.18 より)
追記:後日談「のちの物語」(単行本 1巻 2013.10)が書き継がれている。
↓ ベル・デアボリカの「映画風予告編」 1999冬 ↓