中国における太陽と鳥の信仰(後編1)
★前編では、河姆渡の「太陽を抱く双鳥紋」が良渚の「怪獣と巫」の図像になり、それは龍山期の「鳥と怪獣紋の組合せ」に継承されたことを記した。後編は、さらにその伝統が殷・周を経て漢代に及んでいることを見てゆく。なお、この時代の出来事は、資料はある程度揃っているが、信憑性や解釈をめぐって多くの異論があり、ここに記すのはそのうちの一説にスポットをあてたもの、と予めお含みいただきたい。
はじめに古代中国の形成について大枠に触れておく。中華の代表的な民族といえば漢民族だが、実はその源流はあまり定かでない。全土にわたる統一国家が生まれたのはBC3Cの秦の始皇帝が最初で、続いて漢帝国が成立し、その基盤が確かなものになった。ひとつの国のひとつの民という意識が芽生えた。しかしその実際は、古くから中原に住んだ諸氏族、北方南方の諸族、西方の遊牧民等、さまざまな血と文化を持つ人々が、漢の名の下に共同体としての自覚を持ったということだった。彼らのほとんどは必ずしも中国本土のネイティブだったわけでなく、例えば皆が皆、現代中国人の直接の祖先といわれる山頂洞人(ホモ・サピエンス)の末裔だったのではない。中核を担った氏族にしても、多くは外地の民族に起源するという。
もともと中国大陸に人間は住んでいなかった、か、あるいは住んでいても、ごく小人数の部族が各地にまばらに点在しているに過ぎなかった。彼らがある程度の大きさをもつ勢力に成長したのは、もちろん農耕の発達による生産力の増大と富の集中、そして権力闘争が原動力である。しかし外部からの民族流入も同じくらいに重要な要素であった。例えば、地味に乏しい乾燥した草原地帯で遊牧していた人々が、敵対勢力に追われて東進し、黄河流域の肥沃な土地に至り、農耕民として定住した、といったことが何千年にも亙って繰り返された。彼方より来て定着し、先住民と混じり合い、都市と文化を築いた人々は、さらにその後に来た別の氏族に呑まれ、より大きな共同体が生まれた。さまざまな血、文化、習俗を次々と吸収して膨れ上がってきた。それが古代中国の成り立ちであり、その後も元や清といった異民族の支配下に入ってなお古き伝統を保ち続けた中国の特質である。(備考1)
★前編の最後に辿った龍山文化は、BC2000年頃、別の伝統を持った異文化に交替され、彼の伝統は黄河中流域の二里頭文化(1900?-1500?)に継承された。二里頭遺跡は夏王朝に対応する文化圏と推測されている(もし夏が実在したのならば)。青銅器文化の魁であり、広い領土を統べる王朝に相応しい巨大な城砦都市の嚆矢でもあった。伝説では夏に先立って3皇5帝の時代があり、例えば第四代の帝堯陶唐氏はBC2400年頃の人物と言われているが、夏と同様、今のところ学術的な考証は困難なようだ。
この都市に拠った人々は、西方の一支族だった可能性が強い。彼らは中近東で始まった(らしい)青銅器の冶金技術を持ち、優れた武器と西アジアの優駿を駆使した騎馬戦力とによって、黄河中原を手中に収めた。しかし彼らもさらに後を追ってくる民族には手を焼き、騎馬の来襲に備えて堅固な城砦を築いた…まあ、そんなふうな説がある。
★二里頭文化は二里岡文化に継承された。これは殷代前期の文化中心のひとつである。殷(商)はBC17世紀頃成立した太陽崇拝王朝だった。初代の王、成湯の名は、太陽の日が出る意味の「日偏に易の字」や陽と同音で関係があると「説文」に記されている。湯王は太陽神の末裔を名乗ったらしい。
殷人もまた一説に西方の遊牧民が帰農し、周辺の異民族との婚姻によって勢力を拡大した氏族(子姓族)であった。始祖の契(せつ)は、帝堯の父にあたる帝コクと、蛮族出自の母簡狄の子で、簡狄は玄鳥(燕)の卵を呑んで契を懐妊したと後世に伝わる。以来、燕は瑞鳥とされる。(備考2)
ここで「狄」は、異民族を表すケモノ扁に音符の亦(火は誤った形)を組み合わせた字で、亦(テキ)とは高く抜き出た鳥の尾羽(翟、卓)を意味する。すなわち、頭(の帽子)に鳥の尾羽を掲げた異民族を指す言葉だという。北方の蛮族を後代の中華では北狄と呼ぶが、殷は山東省に拠った氏族と深い親近関係にあり、軍事力の過半を彼らに頼っていた。簡狄の出自はおそらくその周辺(北東方)に勢力を張った氏族のひとつだったとみられ、分(春分・秋分)を司った玄鳥氏以下、多くの氏族が殷の中枢に迎えられている。彼らは鳥を祖霊として信仰していた(玄鳥氏、鳳鳥氏、青鳥氏、丹鳥氏、祝鳩氏といった氏姓は、黄帝の子、小昊金天氏の代に定められた官位名ともいう)。中宗・太戌に仕えて卜占を司った中衍(ちゅうえん)は「鳥身人言」の鳥巫であった。
殷人は当初、黄河北岸に住まったと考えられている(黄河は何度も川筋を変えており、現在の地理とは異なる)。しかし北西方から来襲する遊牧民にたびたび苦しめられて遷都を繰り返した後、ついに幅数キロに及ぶ黄河を渡河して南岸の安陽に至った。それからは比較的平穏な歳月を重ねて実力を養い、周に滅ぼされるまでの273年を殷墟に栄えた。(備考3)
彼らは東方(山東省)の血縁氏族をバックに強大な軍事力を備えていたが、基本的に周辺氏族との巧みな外交によって国を保った。政治決定は巫祝による卜占に委ねられていた。殷墟の遺跡からは卜占に用いられた甲骨が10万片以上回収されている。それは牛の骨や亀の甲羅を火にくべ、熱によって骨がはぜる仕方や割れ目の模様で吉凶を占ったものだ。(備考4)
★卜占の記録(甲骨文字)を調べると、殷人は太陽が没してから次の太陽が現れてくるまでの闇を畏れ、毎日次の太陽は昇ってくるか、「卜夕(ぼくせき)」を繰り返したことが知れるという。「問う。明日、太陽はちゃんと昇ってくるだろうか?」。
10個(十干)の性格の違う太陽が一巡り(旬)すれば、次の旬における天帝の意向を尋ねて「卜旬」を行った。これはその昔、太陽が10個あり、扶桑の大樹から毎日順番に東の空に上ると考えられていたことに符合する(鳥が太陽を運ぶという観念も付随する)。現在四川省や河南省、貴州省など揚子江上〜中流域に残っている十日神話の古型は、当時すでにポピュラーだったようだ。
あるとき、10個の太陽がいっぺんに空に飛び出したことがあった。強烈な太陽の光は地上を焼き、人間は死に絶えそうになった。そのときゲイという神が弓をつがえ、太陽を次々と射落とした。そして最後に一番末の弟の太陽だけが残った、というのが十日神話の主題。
自分も射落とされるのではないかと怖れた末弟が山の下に隠れたため、この世は闇に包まれたというサブ・モチーフが加わることもある。人々は神と相談して飲めや歌えの大宴会を開き、好奇心に駆られて顔を出した末弟を厚くもてなしたので、それからはひとつの太陽だけが毎日天を巡ることとなった。日本のアマテラス大神の天の岩戸伝説を想わせる。
以上の状況証拠から推測すると、殷代には太陽と鳥の信仰があり、おそらく広く民衆レベルで支持されていた。そのため歴代の(おそらく外来の)王たちは、「太陽の子孫=天意を受けた支配者」という称号によって人心掌握を計ったのではないかと考えられる。また鳥信仰の基盤は、北東方の民族(北狄または東夷)から受け継がれたらしいこともわかる。
★次に祭祀器について。卜占に際し、司祭者は火を焚き、天に煙を上げ、酒と肉(羊、牛、豚)とを供えて神や祖霊を歓待した。そのための道具として、青銅製の器(鼎や水差しなど)や玉製の圭(酒柄杓の柄にする)を使用した。また軟玉製の璧や圭・璋(−大汶口文化以来の石斧の柄から転化した瑞玉)を依り代とした。
青銅の鼎(かなえ)は、「鼎の軽重を問う」ということわざがあるように、後代(春秋時代)、国の象徴・正統な統治者の証となったが、元々は神への供え物を盛る器、あるいは農耕の豊穣を祈願する巫具だったと思われる。湯王は、熱しなくても自ら煮炊きし、食物を調達し(中味がなくならない)、勝手に飛んだり歩いたりする鼎を所有していた。そのイメージは北欧神話の巨人イミールの銅鍋に似て、明らかに豊穣の力を引き出すための装置である。
同様に玉製の柄をもった酒器は、玉の持つ霊的な力を神酒に加えるものと考えられたようだ。
器の表面には、装飾的な渦巻きと流紋をまとったトウテツと呼ばれる動物(神獣)や植物、雷、日月星辰(の気)が描かれた。これらの図像は祭祀の対象となるべき存在を表現したもので、例えば龍が描かれた器は龍(神)を祀るために用いられたと解釈される。
★トウテツには1000種を超える数多くのバリエーションが存在し、鳥(鳳凰)、龍、羊、牛など様々な動物がモチーフになっている。これは殷が周辺民族の文化や信仰を積極的に取り入れ、諸族の融和を図ったことに関係していよう(例えば、殷の北西に居住した龍方と呼ばれる異民族は50方国を数え、和するもの敵するもの入り乱れていた。周もそのひとつ)。(備考5)
祭祀には祖霊信仰と自然神信仰の二つの側面がある。殷代初期には双方共に祀られていたが、やがて後者が廃され、末期には祖霊に関わる祭祀のみが行われた。逆に言えばトウテツを構成する鳥や龍は祖霊神(トーテム)であり、彼らを併せ祭ることは平和を維持するに現実的な行事だったといえよう。トウテツはこの時代の最高神、帝の類であるが(「飽くことなき貪欲」(=蛮族)を意味するとの説もある)、同時に各氏族のトーテムの混交体でもあった。代表的な画像を2つ、次に示す。


左は双鳥が互いに外向きに並んだ図像が、同時に羊らしき神獣を構成している合体獣。右は山岳地帯に住む羊かヤギの類の角を持ったトウテツである。トウテツの両側を冠のある外向きの鳥が守っている(この種の図像を判読する時は、まずどこに目があるかを捜すのがコツ)。
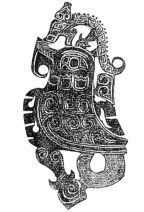 太陽を象徴する二つの目玉、眉間の羽根飾り文様、全身を被う羽根または気を表現する渦巻き模様といった特徴は両者に(多くのトウテツに)共通のもので、かつトウテツの両側に外向きの鳳凰あるいは鼈龍を伴うデザインは、古く河姆渡文化の双鳥紋からはるかに受け継がれてきた伝統に通じる。
太陽を象徴する二つの目玉、眉間の羽根飾り文様、全身を被う羽根または気を表現する渦巻き模様といった特徴は両者に(多くのトウテツに)共通のもので、かつトウテツの両側に外向きの鳳凰あるいは鼈龍を伴うデザインは、古く河姆渡文化の双鳥紋からはるかに受け継がれてきた伝統に通じる。
左図は婦好墓から出た佩玉の拓本である。鳥とミズチ(龍の一種)が描かれている。この鳥はふくろうで(そうは見えないが)、小龍はふくろうに付き従って行動しているのだという。鳥と龍の睦みを表現しているように思われる。
 ★殷代の司祭者を表現するものとして、右の立像にも触れておきたい。「頭に羽根飾りをつけた巫」といわれる像である(軟玉製、婦好墓出土)。ここに見られる羽根の表現は、青銅器や玉器のトウテツ紋、渦巻き紋などに共通の形である。羽には天地の気が宿る。巫師はその力を集めて祭祀を行ったらしい。
★殷代の司祭者を表現するものとして、右の立像にも触れておきたい。「頭に羽根飾りをつけた巫」といわれる像である(軟玉製、婦好墓出土)。ここに見られる羽根の表現は、青銅器や玉器のトウテツ紋、渦巻き紋などに共通の形である。羽には天地の気が宿る。巫師はその力を集めて祭祀を行ったらしい。
もっとも、このデザインは羽飾りでなく、髪の毛を束ねた祭祀用衣装だとの説もある。中国人は古来毛髪を生命力の宿る場所として信仰した。漢代の人々(華北人)は髪を切らず、どんな貧しい人でもきちんと結って帽子(冠)で被っていた。髪を切る刑罰さえあった。おそらく当時にも同様の風習があったのではないかという。(備考6)
いずれにしろ、羽−髪−稲穂・茅・ススキ−組紐の房−吹き流し(旗)といった、風に揺れる毛状のアイテムは生命の気を宿すもの(見えないモノに反応して動きを示す媒体)として等価であるから、これによって期待される効果も同じである。
以上で殷代終り。
備考1:禹(夏)の時代、中国には1万の国があった。湯王(殷)の頃には3000余に減った。さらに武王(周)の時代に1800、東周初年(BC771)に1200、春秋末年(BC481)には100余国にまで減った。そのうち大国に数えられたのはわずか14国である。中国は長い年月をかけて徐々にまとまっていった。このページでは殷、周を主眼に取り上げているが、同時代のほかの国の文化がすべて殷周のそれに近かったかというと、もちろんそうではないだろう。(戻る)
備考2:殷の氏族の起源
ここでは西方起源説をとったが、山東地方との強い結びつきから東方より来た氏族だったとの説も有力。(戻る)
備考3:殷(商)前半期の度重なる遷都は、青銅の材料とする鉱石と鉱山を管理するためだったという魅力的な説もある。(戻る)
備考4:甲骨による卜占
骨卜はBC2〜3000年頃に華北に広まった。初めは亀甲は使われず、骨片に文字を刻むこともなかった。殷代になると、牛/水牛の骨に加えて、亀の甲羅が用いられるようになった。これらの大半は輸入品で、おそらく入手は容易でなかったと考えられる。貴重な甲骨による卜占は、ほとんどが王自身の監督下に行われるものであった。王は卜官を通じて遠い昔の祖先に対して質問を発し、卜人は甲骨に現れた祖霊の答を解釈をした。占った結果は文字にして甲骨に刻まれた。すなわち甲骨文字は、後世の規範とすべく、一族の子孫のために保存された記録であった。なお具体的にどんな模様が吉凶に対応したのかは明らかでない。(戻る)
備考5:鼎に鋳造された神の像
「むかし夏王朝の徳が栄えていた頃、遠方の国々は「物」(ぶつ)の図を献上し、九州(中国の9つの州)が銅を貢納した。そこで鼎を鋳造し、「物」の図をそこにあらわした。そのため諸々の「物」の図が完備した。それでもって人々に善い神と悪い神を認識させることができた。そのために人々は川沢山林に入っても敵対的なものにであったり、その土地土地の神に遭遇したりすることがなくなった。山河の妖怪は現れなかった。こうして天と地の調和が確保され、すべての人は天の加護を享受した」(「左伝 BC606年の記事)
上の引用は、春秋時代の記録保存官みたいな人が、王の諮問に答えて、大昔の出来事を語ったもの。この考えによると、鼎に鋳造された神は必ずしも崇拝すべきものばかりでなく、敬し遠ざけるべき悪玉も描かれたことになる。一方、善玉の神(動物)は単に祖霊(トーテム)というだけでなく−あるいは全く祖霊とは関係なく−、天地を旅する巫をサポートする助手だったとの解釈も十分に考えられるが、このページでは祖霊説をとった。(戻る)
備考6:毛髪信仰
これは漢民族を中心とする華北系の信仰で、揚子江流域の人々にその風習はない。良渚文化人や越人は髪を切っていたと思われる。華北人は南部の断髪を蛮習とみなして軽蔑した。
ちなみに華北はアワ・キビ(畑作)文化圏であり、華南は稲作文化圏で、民族も習俗も昔から決定的に異なる。一体に華北人の気質は華南人よりも烈しい。例えば、華北の仰韶人には首狩りの風があり、大汶口では抜歯や頭部を人為的変形する風があった。殷王朝に交替した後も首狩りは盛んで、奴隷の供犠、人肉食が当たり前だったらしい。(とはいえ、華南には猿の脳みそを食べる風があり、猿を食べるなら人間だって…という説もあり)。
中国南北の対立は古く根深いもので、現代でも華北人は華南人を米ばかり食ってるから軟弱だというし、華南の人は華北の人をイライラして攻撃的過ぎると思っていると聞く。(戻る)