
| 980.水晶(発振子) Quartz (ブラジル産) |

★大分と記憶があやふやなのだが、私が高校の時分は、物理の授業に電磁気学やら誘電体やら電気回路に関する科目があった。なかで一番分かりにくかったのが、コイルとコンデンサを繋いだLC回路だった。回路を流れる電流がバネの単振動に擬えられる挙動を示して、特定の周波数で周期的な変動を繰り返すというオハナシである。
電荷を蓄えたコンデンサは、回路を繋ぐとコイルに向けて徐々に電荷を放出し(電流が流れ)てゆくが、電荷が空になっても電流は止まらず流れ続けて、先とは逆の電位の電荷がコンデンサに戻って蓄えられてゆく。そして元と同じ蓄電量に至ったところで、今度は逆向きの放電が始まって逆向きに電流が流れる。そして最初の電荷状態に戻ると再び同じサイクルを繰り返す。同じ周期で三度、四度…、エネルギー損失なしに永遠にサイクルが続くのだという。
そんなことがありえない(実際は減衰してゆく)のは分かりきったことだが、これは摩擦抵抗ゼロの平面上を物体が永遠に転がり続けるのと同じく、あるいは振り子時計の振り子が位置エネルギーと運動エネルギーをやり取りして同じ振幅で永久に振れ続けるのと同じく、仮想的な理想条件での現象である。
私はこの回路が何の役に立つのかさっぱり分からないまま、目の前にある計算問題をただ解いていた。
社会人になってから与えられた電気回路の入門書には、LC回路(LCR回路)が発振器として出てきて、「磁気エネルギーと静電エネルギーをやり取りする形で固有の周波数の電気振動が持続する。ただし、回路に含まれる抵抗によるエネルギー損失のために振動は減衰する。この消費されるエネルギーに等しい量のエネルギーを外部から補給してやれば振動は持続する。」とあり、用途として「直流の電源から供給される電力を交流の電力に変えるもの」だとあった。しかし私は結局、LC回路を摩訶不思議な理解不能のものとして、日々の忘却にまかせた。(そもそも共振現象自体が驚異的だと思う。)
ともあれ、(持続した交流を作る)発振回路は、特定の周波数の信号を生成したり、より複雑な信号から特定の周波数の信号のみをフィルタリングして取り出すのに利用することが出来るのだそうな。
一方、水晶のような圧電性を持つ物質は、通常は静電容量を持ったコンデンサとして働くのだが、固有振動数によって定まる特定の周波数帯ではコイルと同様の性質(誘導リアクタンス)をもつものとしてふるまう。水晶の物理的(機械的)共振は
LC回路の電気共振と比べると桁違いに周期のゆらぎが少なく、コイルの代わりに発振回路に組み込んで自由振動させると(共振させると)、正確で安定した周波数信号を取り出すことが出来る、のだそうな。現代の電子機器に水晶が広く利用される所以である。
言い換えると、水晶素子に付与される電気エネルギーは逆圧電性によって運動エネルギーに変わり、物理的な共振を惹起し維持する。そして共振する水晶素子はコイルの働きをして
LC(LCR)回路と同様に交流電力を提供するのである。
水晶発振器は、電気回路に同期のための精確な基準信号を与えることが出来るし、高い精度で時を刻むことも出来る。無線通信にも必須のアイテムである。
★一次大戦の頃、フランスのランジュバンは水晶板に高周波変動電圧を印加して共振させ、超音波音源に用いた。cf.
No.979
以来、無線技術者たちの間で圧電体の共振現象が研究されるようになった。米国ではAT&T
ベル電話研究所のA.M.ニコルソンやウェズリアン大学の
W.G.キャディがロッシェル塩を使った研究を行った。キャディは
1919年に周波数制御に水晶を使い始め、その後の3年間に基準信号発生器及び波形フィルターに関するいくつかの論文を書いた。
1923年にはハーバード大学の G.W.ピアースが、一対の電極で挟んだ一枚の水晶板と一個の真空管で構成される発振回路を設計した。これらは世界的にも初期の試みだったようだ。
1926年に AT&Tが所有するニューヨークのラジオ局 WEAFが水晶発振器を使った放送設備を導入したのを皮切りに、米国では数年のうちにすべての放送局がこれに倣った(補記5)。上述の通り
LC回路と比べて水晶発振器の周波数安定性がはるかに優れていたためだが、ただ温度変化による変動は弱点として残り、恒温槽(オーブン)に装入して使用することが前提であった。
この頃までの水晶振動子は、といっても利用はまだほんの数年に過ぎなかったが、
Xカット板のみが用いられていた。それから 1926年に米国光学社の
E.D.ティリヤーが Y軸に垂直に(柱面に平行に)切り出した
Yカット板でも発振が可能であることを見出した。Yカット(ティリヤー・カット)は温度特性が
Xカットより劣ったが、(低電圧でも)発振させやすかった。同じ厚みならより低い周波数で発振した(※Yカットの支配的な振動は厚みすべりモードで、薄板ではXカットと同様に発振周波数が厚みで決まる)。
板の縁部をクランプしても発振するのが最大の利点で、Xカットは縁部の振動をわずかでも抑制すると発振しなかった。
一方、寸法のわずかな違いで発振周波数が大きく変わり、また別の振動モードのオーバートーンが混じるため周波数スペクトラムはよくない。Yカットはやがて回転Yカット系に置き換えられていった。
興味深いことに Xカットと Yカットとは温度特性が逆で、Xカットは温度が上がると共振周波数が下がり、Yカットは上がった。このことから、(ある範囲の)温度変化に対して周波数が安定するカットの方位があるのではないかと考えられるようになった。
この仮説は 1934年にベル研究所のF.R.ラックやG.W.ウィラードらが
ATカットとBTカットを発見(公表)したことで実証された。ベル研では
1929年に W.A.マリソンが、ドーナツ形の振動子が良好な温度安定性を示すことを明らかにしていたが、設計要件が厳しく汎用化に難があった(ちなみにマリソンは
J.ホートンとともに 1927年に世界初の(巨大な)水晶時計を製作している。補記1)。そこで
Yカットを X軸周りに回転させた平板の特性を調べてゆき、この2種のカットに至ったようである。
ATカットは Yカット板を X軸回りに35度15分、奥側(Y軸のマイナス側)に倒した配置である。天然水晶の錘面のひとつ
z面(IEEE標準やJIS標準に言う r面) は Z軸(XZ面)に対して 38度13分の傾きを持つが、これより 3度ほど手前に起こした配置の平板といえる。ATカットの周波数変動は温度に対して三次関数的な特性を持ち、フラットな領域が日常温度(25℃)付近に現れて、-30〜85℃(あるいは
-40〜125℃)の範囲で実用十分な安定性を示す。ただし加工にあたっては切り出し角度の数分の違いが特性に大きく影響する。
BTカットは Yカット板を X軸回りに49度、手前側(Y軸のプラス側)に倒した配置である。こちらも日常温度付近に周波数安定領域を持つ。変動は
ATカットより大きいが、角度の加工精度はさほどシビアでない。なお上記は
JIS標準の座標系での記述である。
加工技術の進歩した今日では、kHz
帯で用いられる時計用の音叉型振動子は別として、MHz帯で用いられる振動子のほどんどが
ATカットを採用している。ATカットの共振周波数は f =
1.67MHz/t (厚みmm)。 cf. No.979 補記2
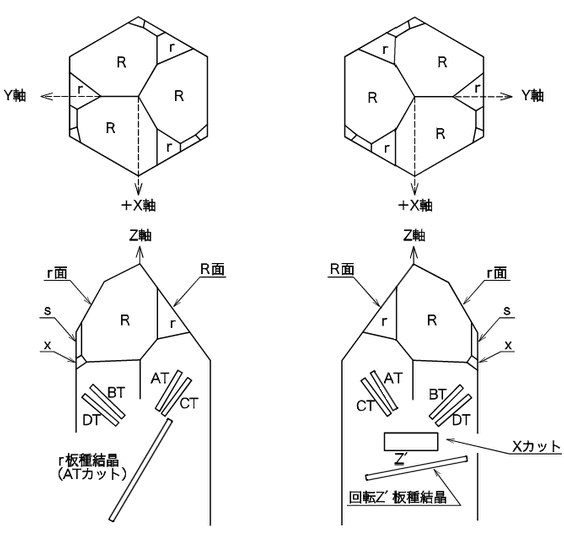
★ところで水晶振動子の研究は日本でも行われていた。古賀逸策(1899-1982)は
1923年から東京市電波研究所に勤めて無線通信の研究に携わった英才で、29年に東工大の助教授となった。高周波通信装置、特に水晶振動子の挙動を理論的に明らめることに強い関心を持った方だったようである。
当時の水晶発振器は設計通りの性能を示すことが必ずしも期待出来ず(発振しないこともあった)、そもそもどんなメカニズム(振動モード)で発振するのか定かでなかったことが、博士の論文から窺える。また日本で使われていた商用通信機はほとんどが米国
RCA社製だったそうだ(補記4)。
古賀が助教授になった頃、世間の景気は低迷していて、懇意の電子機器メーカーの職人を何人か大学で預かることになったという。Xカットの振動子を作るよう指示したところ、誤って
Yカットに切り出してしまった。捨てるのも勿体ないので試しに回路に入れてみたところ、発振したので驚いた。(日本ではまだYカット/ティラー・カットが知られなかったらしい。)
Xカット以外は発振しないと考えていたことが間違いと分かり、Yカット以外の方位も調べたところ、錐面に平行なカット
(R板、R' 板)でもしっかり発振することが分かった(※
R板は r面に平行、R'板は z面に平行)。そして R'カットと
Yカットとで周波数変化の温度特性が正負逆であることに気づいた。R'カットは
YカットをX軸回りに回転させたものに相当するから、両者の間に温度変動がゼロに近い発振可能なカット角度がありうると考えるようになった。
初めは職人に指示してさまざまなカットを作って試してみたが期待する性能は得られず、なにしろ上述のように理論的な裏付けのないところで、得られた結果をどう解釈していいかも判断がつかなかった。そこで水晶のような異方性結晶の厚み振動モードを理論的に解析して、結晶方位と厚み振動の関係式を構築した(1932年)。
Yカット板を X軸回りに回転させた板の等価弾性係数の理論式を導き、温度による変化率がほぼゼロとなる解を計算機を使って探した。結果
35度15分の切り出し角を得た(※数値はZ軸からの傾きとして換算した
-SPS)。
R1板と名付けたこの振動子は良好な温度安定性を示した。上述の
ATカットに相当する。また別の解として XZ面を挟んで逆側に 47度59分の切り出し角を得て
R2板と呼んだ。これは BTカットと等価とされている(※
1度ほど角度が違うが)。
博士が R1板(古賀カット)を得たのは 1932年のことで、1933年の10月に報告がなされた。それから
10日ほど後にドイツのベックマンも、古賀の振動方程式を解いて
R1板/ATカットと等価の解を報告している。また R2板は日本で別のグループがすでに研究していたものである。世の中のニーズを満たす発見は、しばしば同時代的になされるものらしい。
学界の慣習である先着権に鑑みると、古賀の研究発表はベル研に先駆けている。R1板と
R2板は東工大の申請により、「温度無依存水晶振動子」として
2017年に IEEE Milestone
に認定された。学界では(最初の)発見として国際的に認められたわけである。しかし歴史的にみると、世界に広まって科学の進歩に貢献したのは
ATカットであった。
★甲府の水晶加工業者によると、R1板発見の前夜、古賀博士は老舗水晶店の土屋華章をはるばる訪ねて、加工・研磨技術の教えを乞うたと伝わっている。四代目土屋華章は弱冠
25歳の時、金剛砂とモータを使った水晶加工を山梨県で初めて行った人物である。
古賀に師と仰がれた華章は持てる知識を惜しみなく伝授し、また求めに応じてさまざまな角度に水晶を切り出し、精緻な研磨を施した。こうして
R1板が発見されたという。
山梨県は明治維新以来の殖産興業政策に乗って、まず水晶採掘業が興り、次いで地元産水晶を使った加工業が振興した。明治末年には水晶資源が枯渇したが、大正に入って品質の優れたブラジル産水晶を直接輸入出来るようになって一層の繁栄期を迎えた。
水晶発振子の製造には、高品質の水晶と熟練の加工技術が求められる。無線通信が発達した 1930年代以降、最良の素材として世界の注目を集めたのはブラジル産の水晶であるが、その入手ルートが当時の日本にすでに確立していた。またこれを加工する技術が山梨県下に円熟していた。英才の理論を裏付ける良材と職工とが共に揃っていたのだった。
cf. No.935 山梨の水晶加工産業
補記1:ベル研のマリソンらの水晶時計は、Xカットの振動子を 50kHzで共振させた。電子回路を通して周波数を落とし、シンクロ・モータで時計の秒針を回した。精度は日差 0.02秒。年差で7.3秒になる。
補記2:R1板を使用した水晶発振器は 1933年の夏、依佐美無線送信所の設備を使って実験に供された。ドイツの受信局に向けて長波送信を行ったところ、ドイツ側は送信周波数が従来になく安定していることに戸惑い、一時間後、何が起こったのか?と問い合わせてきたという。
補記3:ベル電話研究所では開発されたカットにアルファベット順の符号を付していった。1937年に G.W.ウィラードとS.C.ハイトが CT, DT, ET, FTカットを発表し、1940年に W.P.メイソンが GTカットを発表した。GTカットはこれらのうちもっとも安定した発振子で、基準時間を定める標準器に採用された。
補記4: RCA社(アメリカ・ラジオ会社)は、1919年に GE社が米マルコーニ社を買収して作った会社。
1920-21年に AT&T社、ウェスティングハウス(WH)社等と特許の相互認可協定を結ぶ。この協定により
GEとウェスティングハウスはラジオ受信機の排他的製造権を、RCAはその独占販売権を、AT&Tは放送送信機の製造・リース・排他的販売権を持った(協定を結んでない企業との競争は無論あった)。
協定は 1926年に見直され、AT&Tは国内外の有線・無線電話、有線電信の絶対支配をとり、
RCAは無線電信の独占免許を得た。またAT&Tが送信機製造の絶対権を放棄したため、RCA社はこの分野にも加わった。同年
WEAF局の譲渡を受け、子会社として NBCを設立した。以降、全米各地のラジオ局の多くを傘下に吸収してゆく。受信真空管、ラジオ・セット販売の一大勢力であり、また商業放送ネットワークへ大きな影響力を持った。
補記5:米国初(世界初)の本格的な放送局は、ピッツバークのラジオ・メーカー、ウェスティングハウス社が
1920年に開局したKDKAとするのが定説。自社製品(ラジオ)の宣伝効果によって売上げが増え、経営の採算が合うというポリシーで始められた。最初の放送は大統領選の結果報告だった。
KDKAが送信設備に水晶発振器を採用したのは 1925年といい、ライバル局のWEAFより少し早い。
ニューヨークの
WEAFはAT&Tの子会社として 1922年に開設され、1923年に広告放送を始めた。スポンサーからの収入で運営する商業放送局の嚆矢である。26年
RCAに移管。
ちなみにある統計によると、米国のラジオの生産台数と普及率は、1925年の時点で年産 200万台、普及率 10%、1930年に年産 380万台、普及率 46%。1936年に年産 820万台、普及率は 70% (3,245万世帯)に達した。アメリカ人の生活に、ラジオ放送は欠くべからざるものとなっていた。 (戻る)