
| 981.水晶(圧電性2) Quartz Piezoelectricity (ブラジル産) |



無線通信の歴史は、イタリアの G.マルコーニ(1874-1937)が
1895年に屋外実験に成功したのが画期といわれる。通信距離は約
1.5kmだった。翌年から公開実験を重ねて次第に距離を伸ばしてゆく。
1897年、事業化を志してイギリスにマルコーニ無線電信会社を設立。国際的にも注目を集めるなか、1901年に初の大西洋横断通信を実現させた。当時すでに海底ケーブル網による国際通信が確立していたが、マルコーニは無線による海上公衆通信に市場を見たのだ。やがて船舶の安全確保になくてならない技術とみなされるようになった。
彼の発明はまた軍事戦略を左右するポテンシャルを含んでおり、列強各国は早くから無線技術の取り込みに腐心した。1905年、日本は日露戦争においてバルチック艦隊発見の報を火花式無線電信機を使って打電し、機先を制した。これが無線通信(中波帯)の戦争利用の初めと言われる。
最初期の無線は火花送信機やコヒーラ受信機を用いた非同調式で、超短波や短波帯の電波を用いたが、やがて同調回路が工夫され、ローディングコイルを用いたアンテナが使われるようになって、
1910年代には同調式機器による中波通信が主流となった。同じ頃から長距離通信に長波も実用化されたが、普及したのは一次大戦後のことである。
地表に沿って(昼夜安定して)遠距離まで届く長波はいっとき国際通信の旗手となったが、利用出来るチャンネルが限られ、大電力の巨大送信設備が必要だった。また(環境によって)空電による通信障害が激しいため、1920年代後半からは短波にシフトしてゆく。短波は上空の電離層と地表とで反射を繰り返して遠距離まで伝わる性質があり、かつ小出力でも実用十分だったのである。1927年には英米間で国際無線電話が実用化された。
電気回路の技術を言えば、火花放電によって発生する減衰電波を利用した初期の送信方式は、1904年にポールセンが考案したアーク式発振器や
1907年のウィーン瞬滅火花発振器などが発信する持続電波に置き換わり、その後高周波発電機も登場した。
受信方式はコヒーラ式から鉱石検波式に改良が進んだが(1904-06年頃)、やがて真空管式に移行する。
真空管の発明は鉱石検波器と時期的に並び、1904年のJ.A.フレミングによる二極真空管は検波・整流を可能にし、1906年の
L.
ドフォーレの三極真空管は増幅・発振を容易にするものだったが、実用化は少し遅れた。1910年代前半にA.ラングミュアが開発した三極真空管の優秀な検波・増幅・発振特性が知られて、漸く利用されるようになった。1920年頃には送信装置も真空管式に代わった。真空管は音声信号の無線送信を実現させた。
そうして1920年代後半になると安定した周波数信号を供給する水晶振動子が発振回路に組み込まれる。34年のAT/BTカットの発見は発振周波数の温度依存性を改善した。
20年代から30年代にかけて、水晶発振器の進化は無線通信技術の発達に相伴って進んだといえる。cf.
No.980
水晶振動子はシンプルな部品だが、所期の性能を引き出すのは必ずしも容易でなかった。同じように作っても発振周波数が違ったり、発振しにくかったり、時にはまったく発振しなかった。要因はさまざまあって、全貌が明らかになるのはずっと後のことになるが、少なくとも良質の素材が必須であることはすぐに気づかれた。端的に言えば完璧に均質な単結晶が理想であった。
米国では光学用の素材として従前からブラジル産の高品質水晶を採用していたが(cf.
No.935)、光学グレードの水晶は基本的に振動子にも向いていた。不純物が少なく、クラックや気泡・液泡を含まず、光学的双晶(ブラジル双晶のこと)からフリーな領域を切り出すことが最初のテクニックである。しかし十分ではない。振動子は圧電性/逆圧電性を利用することから、本来的に電気的性質が担保されなければならない。無線技士らが電気的双晶と呼ぶ双晶領域(ドフィーネ双晶のこと)を分離することも必要だった。 cf.
No.972 (ドフィーネ、ブラジル双晶)
次の4つの図は水晶が持つ圧電性の向きと双晶との関係を考察したものである。左上の「右手基準」の図は右手水晶を
Z軸(柱軸/光軸/c軸)に垂直に輪切りにしたものを JIS標準の
X-Y座標軸上に配置し、X軸方向に圧縮した時に現れる電荷を記してある。淡紅色の四角形はX軸に垂直にカットした断片のモデルで、X軸正側の面に(+)、負側の面に(−)が現れる。
右上の図は「右手基準」の結晶を Z軸周りに 180度回転させた配置である。右手水晶がドフィーネ双晶(電気的双晶)をなす時は、左上図の領域と右上図の領域とが入り混じることになる。左上図の淡紅色の領域を、右上図の結晶で同様にカットすると淡緑色部のようで、現れる電荷の向きが逆になる。すなわち右手ドフィーネ双晶において、双晶領域をまたいでカットした水晶板は圧電性(の幾分か)が減殺されるのである。左手ドフィーネ双晶でも同じ議論が成立する。
左下の「左手基準」の図は、左手水晶をJIS標準の X-Y座標軸上に配置し、X軸方向に圧縮した時に現れる電荷を記してある。ブラジル双晶(光学双晶)においては、左上図の領域と左下図の領域とが入り混じることになる。左上図の淡紅色の領域を、左下図の結晶で同様にカットすると淡青色のようで、現れる電荷の向きが逆になっている。すなわちブラジル双晶において、双晶領域をまたいでカットした水晶板はやはり圧電性(の幾分か)が減殺されるのである。
こうした現象を予め排除するには、前述の通り、まず光学双晶フリーの領域を切り出し、次いで電気的双晶の領域を跨がないように振動子をカット取りするべきなのだ。(また光学的双晶の境界は結晶構造上の欠陥の巣であり、振動性に物理的な悪影響を及ぼす。)
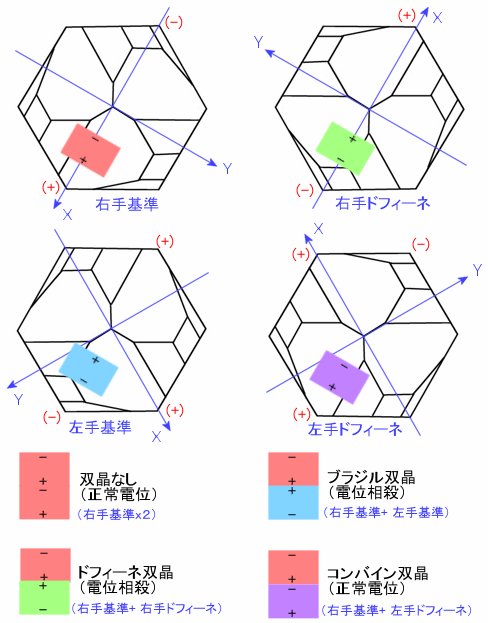
そして水晶の圧電性の向きや物理的な振動特性は、結晶構造の方位に支配されているため、振動子をカットする方向/角度は基準軸に対して厳密に定められなければならない。しかし水晶の原石に予め基準軸が描いてあるわけではないから、軸を割り出すことも仕事のうちである。
初期には結晶面(錐面)が出ている原石だけをカットした。光学的な検査によってZ軸(光軸)を判断した後は、X軸(あるいはY軸)の方向を知るのに錐面が重要な指標とされたのである。しかし軸を精確に定めることが出来るようになるには
X線回折による検査法の確立を待たねばならなかった。