★先の週末、テレビで宮崎駿の「耳をすませば」をやっていた。ロードショーに掛かった時はさほどと思わなかったのだが、2回、3回と繰り返し見るうち、だんだん好きになった映画だ。もちろん今回も見た。よかった。
この作品には、ここに根づいている雰囲気、好きなものを見つけてゆこうとする憧れ、純粋な気持ちを守ろうとする強さがある。と思う。そして清々しい。
また、鉱物好きの心をくすぐる映画でもある。ギャラリーNo.121にエメラルドの原石をめぐる会話を紹介したが、このエピソードの後に、猫人形の男爵と一緒に主人公の雫が空に浮かび、上昇し、風のように宙を滑り、遠い魔法都市を訪れて、ラピスラズリの原石を探すシーンが続く。
「いざ、お供つかまつらん。ラピスラズリの鉱脈を探す旅に」
少しばかり気取ったふりの男爵は、彼が誕生した異国の町まで雫をいざなうが、なんだかよく分からない展開によって、そこから先、ただ一つのほんものの原石を見つけ出す作業は、彼女が一人でやり遂げねばならない。これは雫が書こうとしているお話なのだが、現実世界での彼女の心の動きにも呼応しており、ストーリーの進展に重要な役割を担っている。
ところで、雫はラピスラズリ−砂漠の夜空に喩えられる、金梨子を散りばめた群青色の石−を見たことがあるのだろうか。多分、あったのだろう。
あるいは見ていないとしても、いつか耳にしたラピスラズリという宝石のエキゾチックな響きが、彼女の心にロマンチックな夢を掻き立てたことがあったに違いない。そして、その夢は西老人が見せてくれたエメラルドの原石に触発され、アラビアンナイトのランプの煙のように、記憶の底からいまふたたび立ち上ってきたのだと思われる。
実際、呪文のような言葉、ラピスラズリをつぶやく時、ひとはまだ見たことのないバダフシャンの奥地、この青い石のふるさとに想いを馳せずにいられるだろうか。コクチャ川が刻む峡谷の踏み分け道を、いつか自分も辿ってみたいと願わない鉱物愛好家があるだろうか。(いや、ない)
そしてもし、現実にその一歩を踏み出すことになれば、私たちは男爵のような頼もしいガイドを味方にし、雫のような怖れを知らぬ冒険心のありったけを奮い起こさねばならないだろう。そこは現代でもなお、辿り着くことの困難な秘境なのだから。

ラピスラズリ −アフガニスタン、バダフシャン産
参照 ギャラリーNo.293
★ラピスラズリの歴史を簡単に振り返ってみよう。
この石を使った細工物がBC3500年頃、都市に住むシュメール人の間に広まっていたのは間違いのないところである。鉱山が発見されたのは一説にBC4000年頃だったという。
産地はアムダリヤ河の上流、コクチャ川を遡った峡谷。標高3,500〜5,000mの峰を連ねるヒンズークシュ山脈の懐深く、一年の半ばを雪に閉ざされた山岳地である。
わざわざ好んで分け入る行楽地でもなければ、住みたいと願う天府でもない。そんな荒地にラピスラズリを見つけたのは、行方定めぬ旅人か流浪の民か、あるいは他人の監視を避けてヒマラヤ越えの交易ルートを開発しようとした商人、さてはまた金属鉱石を求めて人跡まれな山中に脈を追った鉱山師といった人々であったろうか。もし最後の者だったとすれば、この石が普及した年代には興味深い一致がある。ちょうどその頃、中近東で銅(青銅)の精錬が始まっているのだ。
この時からおよそ6000年、コクチャ川沿いの険しい隘路を辿る者は、あらゆる時代に絶えなかったように見える。ラピスラズリはBC3000年頃までにエジプトに伝わり、2,000年以上の長きにわたって、王家の装束や墳墓の副葬品に用いられた。ミイラの心臓の上には、復活の願いをこめて刻んだ護符が乗せられた。メソポタミアでは、BC2500年頃の古代遺跡にラピスラズリの装身具が見られるという。
BC4世紀にはギリシャの人々がこの青い石を愛好し(備考1)、その後ローマ人の間でも広く知られた。
AD5世紀になると、ラピスラズリを擂り潰した顔料ウルトラマリンがヨーロッパで使われ始める。この顔料は、1826年にJ.B.ギメが合成品を発明するまで、たいへんな貴重品として扱われた。
一方中国では、BC 6世紀頃−孔子の時代−までにラピスラズリが伝わっていたとの説がある。とすれば当時すでに中央アジアを起点に、西はエジプト、東は中国まで、東西を結ぶ広域流通ネットワークが存在していたことになろう。もっとも、インドから東側の一元交易ルートが確立するのは、軟玉の話1で書いたように、前漢の武帝の時代(BC
2世紀)以降のことなのだが。
時代が降って唐代になると、イラン系の人々と中国人との交流はそう珍しくなく、ラピスラズリを化粧に使う女性も現れたようだ(No.96)。もちろん細工物にも重宝された。正倉院御物のひとつ、平螺鈿背円鏡(背面に螺鈿や象嵌を施した円鏡)には、ラピスラズリや琥珀が象嵌されているが、それぞれバダフシャン産、ミャンマー産であることが判明している。この石はとうとう日本にまで達したのだ。
★このように世界中で愛好されたラピスラズリだが、産地に関する情報が外部に知られることはほとんどなかったようだ。これはむしろ交易の性格として当たり前のことで、付加価値の高い特産物は、どんな国でも厳重に産地や製法を秘匿し、流通量を管理し、そうすることで権益を守ったのである。従ってラピスラズリに関する古い地誌も、たいてい漠然とした内容にとどまっている。
例えば、「漢書」西域伝のカシミール地方の項に、この国の産物として琥珀の次に「璧流離」が挙げられているという。流離は瑠璃のことで、ラピスラズリを意味するが、ただ名を述べたにすぎない(ちなみに唐代になると瑠璃は各色のローマガラスを指す)。
「大唐西域記」の屈浪ダ国(現在のバダフシャンの一部にあたる)の項に、「山巌の中に多く金精を出だす有り。その石を琢折し、然る後に之を得る」があり、金精は金鉱かもしれないが、ラピスラズリの可能性が高いと言われている。これも「山の中に石があって、それを割ると金精が入っている」というだけで具体性がない。
南宋紹興 3年(1133年)の序がついた「雲林石譜」には、「于闐(ホータン)国、堅土中より出で、色深きこと藍黛(らんたい)の如し。一品は斑爛(斓)白脈、点々として光を燦かす。これを金星石という。一品は色深碧にして光潤あり、これを翡翠という。」とあり、金星石はラピスラズリだろうという。斑斓は彩り豊かで美しい意。白い脈も入って点々と輝くのだから、No.293の二番目の画像のような黄鉄鉱混じりの青金石と思しい。藍黛という以上はかなり色目の暗い青色だろう。これは下級品。もう一つは深い青色で光沢に艶のある上品、カワセミの羽の青色に擬えて翡翠と呼ばれる。続けて、屡试之,正可屑金(何度も試しているとまさに金が削れる)とある。この語は後の本草綱目や物理小識に「金屑之翡翠」の成句で現れ、いつしかひすい輝石の特性のようにみなされる。キズのないものは少量しか得られないので、産地では翡翠を貴とし金星石を賤とする、と述べられている。cf.
ひすいの話4
いかにもホータン産の石のように受け取れるが、実際にはホータンを経由して中国に渡ったと考えるのが妥当だ。
有名なところでは、マルコポーロの旅の記録「東方見聞録」に、中国への往路、一行がラピスラズリ鉱山に立ち寄った記述があると言われている。19世紀の宝石の権威ストリーターの著書に、「1271年にダッタン国を訪問したとき通ったことがある」と書いてあるそうで、日本の宝石・鉱物書はほとんどこれに右ならえしている。
けれども、私が見聞録(平凡社の完訳版)を読み返した限りでは、該当する文章がどこにあるのか分からない。バダフシャンの項には、シグナンに産するバラスルビーについてやや詳しい説明がされた後、「またその質の佳良なること世界無比を誇る群青(Azure)の原石を出す山もある。この群青の原石は、一般の岩石層と並んで山中に鉱脈をなしている。」とあるだけだ。(群青とは、「回回青(コバルト系顔料)か無名異(褐鉄鉱の一種)であろう」とか、「サファイヤか藍銅鉱だろう」とか、本によってさまざまに解釈されているが、さすがにラピスラズリのことと思われる。)
先行する中国の記録同様、実地を訪ねたとは思えない簡素さだ。もっとも、東方見聞録は異本が
6類140余種に上るというから、テキストのどれかにそれらしい記述があるのかもしれない。
ただ、彼らがイタリアを出発したのは1270年の末であり、翌
71年の秋にはまだシリアにいたのだから、年内にパミール高原の手前まで旅程を稼ぎ、冬の山岳をおして鉱山を訪問したと考えるのはちょっと無理がある。またマルコはバダフシャンの手前で体調を崩し、1年弱の間病床に臥せっていた。もし鉱山を訪れたとしても、71年中に実現したはずはない。
ついでにいえば、もともと一行はペルシャ湾のホルムズから海路を行く予定だった。ところが、乗るはずの船があまりにぼろっちいのに怖れをなし、急遽陸路に変更したのである。だから、鉱山訪問が当初の予定になかったことも確かだ。
それはそれとして、彼らの旅程を辿ってみると、ホルムズを発ってから、ケルマン(キルマーン)→コビナン→シバルガン(サプルガン)→バルク(かつてのバクトリアの首都)→タイカン(タリカン)→バラシャン(バダフシャン)→パシャイ→ヴォカン(ワカン/ワハン)→パミール→ベロール(ボロール)→カスカール(カシュガル)と進んでいる。
西方からカシュガルに向かうシルクロードは、アムダリア河の北側をブハラ→サマルカンド→フェルガナと進み、ソグディアナを通ってパミール高原の北を抜けるのが主要ルートであるが、彼らはホルムズから陸路を選んだため、シバルガンまで北上した後アムダリア河の南側を東進することになった。そしてパミール高原の南端とヒンズークシュ山脈の北麓に挟まれたワカン峡谷の間道を伝ってタクラマカン砂漠に出た。いわば裏道を行ったわけだ。しかしこのワカン回廊は、古来ラピスラズリが中国へ運ばれた通商路でもあったのだ(玄奘三蔵も通った)。
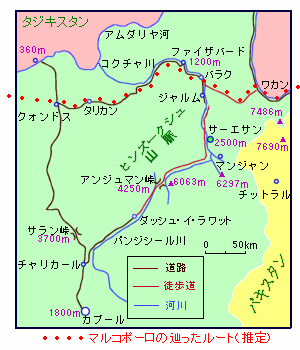
左の地図に、マルコらが通ったルートの一部を赤い点線で示した(図中の道路、徒歩道、河川は1970年頃のもの)。
当時のラピスラズリ鉱山はサーエサン(サレサン/サリサング)、またはその付近にあったと考えられる。北方約50キロのジャルム(ジュルム/ジェルム)は最初の集散地であり、ラピスラズリはこの村を発して、東へはバラクからワカン峡谷を抜けて、カシュガルやホータン経由で中国に送られたとみられる。
♪ラピスロード この道 ずっと 行けば 中国に 続いている 気がする ラピスロード。
また西方へは、ファイザバードからクォンドス(クンズーツ)、そしてアムダリヤ河に出てブハラに運ばれたとされる。ここからヨーロッパ方面だけでなく、再び東の中国に向けて運ばれたラピスラズリもあっただろう。
このように、一行は鉱山から70キロほどの地点(バラク)を通過し、ラピスラズリが開いた交易路を利用して中国を目指したのであった。バラクからは片道3日ほど費やせば鉱山に足を伸ばすことも可能だったろう。実際に足を伸ばしたか否かは歴史のロマンであるが、いずれにしてもマルコは鉱山について詳細な記録を残さなかった(ようだ)。そして彼ら以降、ラピスロードを辿って産地に接近した旅人はずっと後世になるまで現れない。
こうしてみると、ラピスラズリの影響が世界中に広がった一方、鉱山を訪れた外国人は、おそらく数えるほどしかいなかったと考えてよいだろう。ラピスラズリの産地は、長い間、外の世界にとって幻であり続けたのだ。
★鉱山への訪問をはっきりと記録した西洋人は19世紀になってやっと現れる。イギリス東インド会社の若い士官ジョン・ウッド大尉だ。
ヒンズー・クシュ山脈の峠路の調査を命ぜられたウッドは、1836年から38年にかけて、アムダリア河(オクサス河)源流の探査を単独で行った。その途次、パミール南路のジャルムの領主と交渉し、ラピスラズリ鉱山に入る許可を得たのだった。
彼は険しい岩山を踏破して(数年前の地震で道が崩れていたため、非常に困難であった)、ようやくのことで深い渓谷に面した鉱山にたどり着いた。そこでは石灰岩の地層に鉱脈が貫入し、割れ目にいくすじもの縞模様がついていた。坑道は原始的なもので、絶えず落盤の危険にさらされていた。実際、崩落した岩が行く手を狭め、這って進むよりない箇所もあった。暗い坑道の奥で、鉱夫たちは原石のある場所を見つけては枯草を燃やし、岩の表面を暖め、これをハンマーで砕いていたという。
その見聞は1841年に出版された「オクサス河源流行」という紀行にまとめられた。
実はそれまで土地の領主は代々排他的で、鉱山を厳重に管理し、住民が勝手に掘ることを禁じてきた。しかも残酷だったので、旅行者もなかなか近寄れなかった。しかし当時はラピスラズリの収量が減少し、質の劣る鉱脈しか見つからなくなったため、鉱山経営に対する領主の興味が薄れていたという。そうでなければ、ウッドは産地に近づくことも許されなかったであろう。
このことは、ラピスラズリがいつでも潤沢に供給されてきたわけではないことを示唆している。過去6000年の間には、大量に採掘された時代もあれば、新しい鉱脈が発見される迄、細々とズリ(質の劣る原石は谷底に放り捨てられた)を拾った時代もあっただろう。(備考2)
★ウッドの記録から察せられるように、ラピスラズリ鉱山は地理的な条件と人為的な規制によって、幾世紀もの間、外界の進歩から取り残されてきた。その事情は現代になってもさほど変わっていないようだ。堅い岩石を崩すための火と水はダイナマイトに変わったが、鉱山の機械化・近代化は地理的に困難であり、今も昔ながらの手掘り作業が行われている。鉱山へのアクセスや原石の輸送には車が使われるようになったが、それでも車が通行可能な道路と鉱山との間には、依然何十キロもの険しい山岳路が横たわっているのである。また車道といっても、幹線道以外は、かろうじて通れるレベルであることに留意しなければならない。
最新の情報とは言えないのだが、1970年頃行われた調査報告の資料があるので、それに拠って、首都カブール(当時の正規輸出拠点)から鉱山のあるサーエサンへの道程を記してみよう。上掲の地図をご参照願う。可能なルートは2つある。
一つはチャリカールからパンジシール峡谷を越え、ダッシュ・イ・ラワットまで
160キロをジープで走り、ここから徒歩または馬でアンジュマン峠を越えて渓谷沿いに鉱山を目指すルート(通称アンジュマン街道)。車を降りた後、後半の135キロを踏破するのに相当の日数(1週間以上)と体力を要する。(資料は、いずれ全行程をジープで行けるであろうとしているので、今ではもう少し楽になっているかもしれない)
もう一つはサラン峠を越えてクォンドス(クンズーツ)に抜け、ファイザバードからジャルムに至る山岳ルート。ジープはジャルムより2,3キロ先のハズラ・サイド(ハザライサート)まで入り込めるが、カブールからの走行距離は
750キロに達し、しかもクォンドスから先かなりの悪路を覚悟しなければならない。ハズラ・サイドから鉱山まで
40キロ。幅の狭い荒れた道をロバや馬を連れて歩いて登る。最速
4日で辿り着くという。
どちらのルートも気候的な条件(積雪)により、通行可能な期間は
6月から 11月までに限られる。この間の 5ケ月ほどが採掘シーズンとなり、シーズンが終わると鉱夫たちは山を降りる(冬期は盗掘シーズンという説もあるが)。コクチャ川の右岸、海抜2,500mの地点に国営鉱山のキャンプが設営され、鉱夫らはキャンプの上手、数百mの地点にある鉱脈へ、ロバも通れない道なき道、というか崖を登ってゆく。掘り出されたラピスラズリは人夫がキャンプまで背負って降り、そこでロバの背に載せ替えてハズラ・サイドに運ぶ。そして二番目のルートでカブールに搬送する。通常のべ
9日以上を要する。
ラピスラズリの産地というのは、ざっと、このような僻地に存在しているのだ。観光気分ではとても行き着けない。
それゆえ、私がラピスラズリの鉱脈を探しにゆくときは、それなりの覚悟を決めて旅立つ所存であるが、なろうことならジッキンゲン男爵を水先案内とするあなたのお供に加わり、午後の乱れた気流に乗って、ヒンズークシュの山群をいっきに飛び越えてゆきたいと願う次第であります、雫さま。
(2004.3.28)
備考1:プリニウスの「博物誌」は、サッフィール(サッピルス)の名でラピスラズリを載せている。「金が点になって光っている」、「最良のものはペルシャで発見される」とある。
「群星きらめく夜空」にたとえているとの説が宝石書一般に採用されているが、これはどこに書いてあるのか見当たらない。 (戻る)
備考2:もっとも古い鉱山のひとつとして、ダレーズー(Darreh-Zu)が知られているが、ずっと昔に枯渇したという。ジョン・ウッドが訪問したのは、「フィルガム(Firgamu)に近い鉱山」として参照される。現在はサー・エ・サン(Sar-e-sang)がもっとも有名な鉱山となっている。ここではラピスラズリの結晶(ギャラリーNo.250)も見つかっている。ほかにも稼動している鉱山があるかどうかは知らない。
1970年代のラピスラズリの供給量は、表向き年平均1トンほどであった。しかし79年末にソビエトがアフガニスタンに侵攻すると、数倍に膨れ上がった。地理的な悪条件が幸いしてか、鉱山は占領後も体制側の管理下におかれず、もっぱら抵抗運動の資金源として採掘されたようだ。ナショナリストたちはパキスタンとの国境を越えてせっせとラピスラズリを運び出し、武器に変えた。一方体制側も同じような発想で国内の貯鉱を放出した。そのため、80年代は近年になく大量のラピスラズリが市場にあふれ出たのであった。とはいえ、質のよい原石がそうそうあろうはずはなく、多くは品質的に感心しないものだったという。
ちなみにパキスタン側の集散地ペシャワールとサーエサン間はロバに乗って1週間以上の行程という。ラピスラズリをはじめ、アフガニスタン産の宝石鉱物、例えばジェグダレクのルビー、パンジシール峡谷のエメラルドなどは、現在でもカブールから出荷されるものより、ペシャワール経由で市場(カラチ、ニューデリー)に出るものの方が多いようだ。また高品質のものは直接ヨーロッパに送られることもあるという。(戻る)
備考3:青金石の和名だが、鉱物和名辞典(1959)に、古来その顔料を群青、空青と呼んだとあるが、藍銅鉱やコバルト顔料との混同があったように思われる。辞典には、その他、「琉璃」、「催生石」、「璻林」、「流離」、「青黛」、「金精」、「青玉」が挙げられている。
補遺:ウッド大尉は上記紀行書の中で、「死にたくなかったら、コクチャ渓谷に近づくな」と警告している。それでも自分は渓谷を進み、ラピスラズリ鉱山をその目で見た。ついでに言えば、その昔アフガニスタン人は、「死にたければ、クォンドス(クンズーツ)へ行け」といったらしい。ロシアの鉱物学者たちは、1930年頃、コクチャ渓谷よりさらに辺鄙なパミール高原の只中に踏み込んで、ラピスラズリの鉱脈を発見した。やはり情熱であろう。
参考:「シルクロード見聞録」(松崎哲様のサイト)に、古代のラピス・ラズリの交流を巡る素敵なエッセイがあります。リンク許可いただきました。
⇒ ラピス・ラズリに夢を托して ラピス・ラズリの道