
| 723.苦灰石 Dolomite (モロッコ産ほか) |



古い鉱物書を開くと、ドロマイト(苦灰石)は、方解石
CaCO3
と菱苦土石 MgCO3
の複塩と考えられ、これが本鉱の組成にあたる、と記述されている。
方解石と菱苦土石の結晶構造は同形だから、カルシウムとマグネシウムの比率は互いの理想組成を端成分として比較的自由に変動しうるのではないか、なぜ複塩といえるのか、という疑問が起こるが、実際、純粋なドロマイトはおおむね54%の炭酸カルシウム、46%の炭酸マグネシウムを含んでいる。つまり1:1である。そしてマグネシウム成分が鉄(やマンガン)に交代した変種のアンケル石(やクトナホラ石)では、(MgO+FeO+MnO):
CaO =
1:1の関係が成り立つ。従ってドロマイトはやはり複塩である、という。(ただしアンケル石やクトナホラ石との間に広い範囲に連続固溶領域が存在する。また高温生成のものはCa過剰になる。)
結晶構造は方解石や菱苦土石によく似ているが、対称性の程度はやや異なる(別の三方晶系型の群に属する)。そのことは時にドロマイトが作る二連(三連)の菱面体貫入双晶の形、上の2番目の画像に示すような「く」の字形の連晶、それが両端で反転して組み合わさった鞍形を示すこと、あるいはまれに大きな単結晶を発達させることに反映されている。
湾曲した連晶は結晶が平行に重ならず、少しずつあるべきポジションからずれて成長していった結果で、同様の累積変位は、束沸石のリボン状の集合、ある種の煙水晶の連晶(グウィンデル)、輝沸石のカーブを描く連晶などにもみられるが、鞍形は私の知る限り、ドロマイトの際立った特徴のように思われる。方解石にしばしばみられる層状の平行双晶はドロマイトでは存在しない。結晶構造の違いから独立種として扱われている。 cf.
ウィーンNHM蔵(菱鉄鉱)
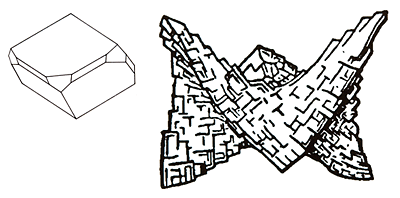
ドロマイトは交代作用によって石灰岩(方解石やあられ石)から二次的に生成(苦灰化・白雲化)するものと、沈殿作用によって一次的に生成するものとがある。方解石とドロマイトの炭酸水に対する溶解度は異なり、常温の飽和炭酸水では前者は後者の3〜4倍の量が溶け込みうる。この性質がドロマイトの生成に寄与しているとみられる。蒸発岩に伴う場合もある。
石灰岩の露頭は風化面が蝋のように滑らかだが、浸食に強い苦灰岩のそれはざらついた組織を呈し、象皮構造と呼ばれている(ただし結晶質石灰石も同様の構造を示すことがある)。
塩酸に対する反応性も異なり、方解石は純度の高いものほど容易に発泡するが、不純物が増えると泡が出にくくなる。一方純度の高いドロマイトは濃塩酸でも発泡が小さく数も少ない。粉末にするか、塩酸を温めておくと発泡しやすくなる。
本鉱の発見は、フランス、ドフィーネ生まれのフィールド鉱物学者、デオダ・ドゥ・ドロミュー(1750-1801)に負っている。時間があれば野外調査に出かけていた彼は、あるときチロル・アルプス(今のイタリア側)を調査していて石灰性の岩体を見つけたが、方解石と異なり希塩酸に対する発泡を示さなかった。この観察は1791年にフランスの著名な科学誌に報告され、翌年春にはソーシュールがこの石をドロマイトと命名した。また今日この岩体が発見された山地はドロミティと呼ばれている。世界遺産である。
ちなみに、酸による発泡を示さない石灰質岩があることは、実はリンネが先に報告していたと言われている。
通常ガラス光沢だが、ときに真珠光沢を示すものがあり、欧州ではパール・スパーと呼ばれた。真珠光沢は湾曲性の結晶に顕著で、ここにあげた画像でもモロッコ産は真珠光沢を示している。和名の苦灰石は成分に拠るもので、マグネシウム(塩)は舐めると苦いために苦しい名が与えられているが、欧州でも Bitter Spar の異称がある。その外観から白雲石の名もある。白雲石は中国での呼び名が日本でも通用していたものだが、今は一般的でない。おそらく3番目の画像のような、白い擦りガラスに似た平澄な感じに依るのだろう。
※いわゆる苦灰岩のカルシウムとマグネシウムの組成比率は必ずしも1:1でなく、マグネシウム分が随分少ないものもある。この種の岩石は苦灰岩質石灰岩と記述されるべきものだろう。
補記:海水中でサンゴ礁石灰岩などを交代して生成したものの中には、結晶度が低く少量の水分を含むもの(プロト苦灰石と称する)があるというが、はっきりしていない。
cf. ヘオミネロ博物館3