
| 1030.煙水晶(鱗形の肩の小面) Smoky Quartz rare faces (USA産) |


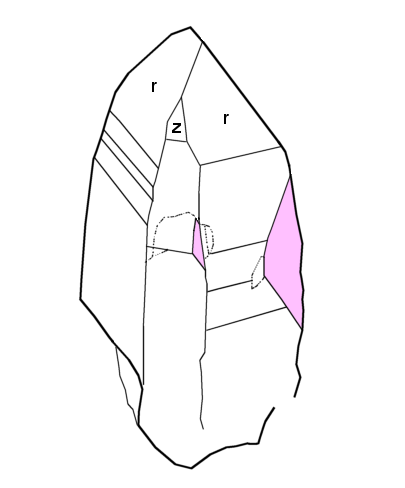

レイク・ジョージやフロリサント北方の「クリスタルピーク鉱山地域」はパーク郡とテラー郡とに跨って広がるペグマタイト鉱物の名産地だ。アマゾナイトの美晶を産したかのツーポイント鉱山はパイク国有森林公園内にある。
1870年代、すでに金鉱探しや遊山客たちが土産物になる結晶を漁ってジョージ湖周辺の丘やクリスタルピークを歩き回っていたといい、同じ頃、フート鉱物標本社は宝石質のトパーズや水晶を求めてクリスタルピークでの採集を試みていた。当時はアマゾナイトに注目する人は少なく、しばしばズリに捨てて顧みられなかったそうだが、1893年のシカゴ万博に美麗結晶が出品されたことでその経済価値が認知された。
1970年代になると鮮やかな青碧色のアマゾナイトに暗色の煙水晶を伴うコンビネーション標本が市場に出回り、色彩対比の妙を得た逸品として高く評価されるようになった。90年代末にはこのタイプの標本を狙った商業採集も行われた。
これらの結晶鉱物を求めて地域の山野を跋渉し、晶洞を探るアマ/プロ採集者の姿は、1世紀以上にわたって絶えることがないという。cf.
No.700
画像の標本はレイク・ジョージ産と標識された煙水晶で、1993年に採集されたもの。丈
3cm
ほどの小ぶり品ながら、結晶面・稜線ともに整って好ましい。対向する一対の錐面の合せ面が平行に伸びたタガネ形の扁平な単結晶形で、錐面の下には大傾斜面が続き、軽くうねりつつ勾配を変えて角柱部分を構成している。
タガネ形の水晶は、ときに主錐面(r面)と副錐面(z面)との判別が難しい。
錐面の会合する頂点を持つ普通の水晶は、3つの主錐面が頂点を構成する面となり、一方副錐面(のうちいくつか)は頂点に達しないことが多い。頂点を構成しない錐面があれば副錐面と仮定し、それ(ら)と一つおきに配置した錐面も(頂点に達していても)副錐面と仮定することが出来る。そして副錐面を挟んで配置する3つの面を主錐面とみなせば一応の整合性がとれる。
ところがタガネ形の単結晶形では、タガネの刃をつくる対向する錐面が同等の大きさに発達して、どちらが
r面とも(もう一方が z面とは)言い難い形状になりがちなのだ。それらの両側にある錐面のペアも同等の形状をとると、判別の根拠がまったく掴めなくなってしまうが、そういう形態がかなりの頻度で見出される。
古い鉱物書には、r面と z面とが交互に配置することを要件とせず、主錐面的な形態の面はすべて
r面、副錐面的な形態の面はすべて z面として扱ったものがある(Dana
7th
のように、どちらだかあえて明示しないケースもあるが)。
r/zの別を形態的な特徴として(のみ)扱うならば、このやり方は正しい。
一方、r/z面の区別を結晶構造的に考えると、単結晶において両者は柱軸回りに
60度回転した位置で交互に現れるはずだ。しかし実際の水晶はしばしばドフィーネ双晶領域が不定の境界線を伴って入り混じっているから、主/副錐面の形態は必ずしも単結晶の場合と同じであると限らない。r面的な
z面、z面的な r面の形態がありうるだろう。タガネ形や平板状の結晶形はむしろそのように考えないと形態の説明がつきにくい。
さて、この標本は線図に示したように柱面に(淡赤紫色の)鱗形の小面が現れている。標準的な結晶形(※錐面と柱面(m面)とで構成される形)では、錐面の直下に三角形状で現れる面だが、大傾斜面を伴う結晶形ではしばしば錐面から離れた下方に生じて、かつ半楕円式の多角線と柱面間の稜線とで限られた特徴的な鱗形をなす。No.1029で「ぜいご形」と呼称した面群はこの鱗が平行連晶した集合形である。
柱面の途中に面が現れるなんておかしな感じがするが、注意して観察すると、案外そういう特徴を持った標本にでくわすものだ。お手元の標本を確認されたい。