
| 938.水晶 日本式双晶2 Quartz Japan law twins (ペルー産) |




18世紀中頃から19世紀初に体系化が始まった吹管分析や元素概念の形成と組成分析は、鉱物に関する化学的知識の蓄積を促した。一方で自形結晶の形状定義や面角の測定・光学特性の研究は、結晶学的知識の蓄積を促した。20世紀にX線回折による構造解析が始まるまで、ひとつの鉱物種(species)における新たな形態(双晶を含む)や条線・蝕像・結晶面の発見は、重要な知見として熱心に追及されたのだった。
水晶は二酸化珪素 SiO2という単純な組成の鉱物ながら、直観的な理解を阻む螺旋型の結晶構造を持ち(左水晶と右水晶とがある)、形態(晶癖・成長集形)が多彩で、他の一般的な種にない奇妙な双晶様式も発現する。フロンデルは
Dana 7th (1962)に112種の面が確からしいことや 80種類の形態を掲げている。
古来、中国から水晶の大産地と見なされた日本では、幕末から明治にかけて米欧との接触により大きな水晶市場が拓け、山梨県(甲斐)などで盛んに採掘して輸出した。傍ら欧米の学者たちは研究のために頻りと日本産の鉱物標本を求めた。彼らにとって未知の土地の産物はつねに発見の宝庫だったのである。
そうした流れの中でさまざまな日本の鉱産物があちゃらの博物館や収集家の耳目を集めた。金峰山の水晶のほか、市ノ川の輝安鉱や苗木・田ノ上のトパーズ、赤谷の自然砒はその代表格といえる。逆に欧米の関心に刺激されて、日本国内でも特産鉱物への愛着が育った。(cf.
明治時代の有名鉱物)
金峰山の水晶鉱山はすでに幕末にドイツ人が視察に来たといい、明治7年(1874年)にはドイツ公使が甲府を訪れて原石を購っていった(cf. No.813 追記)。 一方、函館に住んだモーニッケ氏が本国にもたらした風変りな形の甲斐産水晶は珍しい傾軸式の双晶で、1874-75年頃、G.von. ラート博士がハート形(心臓形)双晶と呼んで報告した。以来、甲斐産水晶標本の需要がドイツを中心にヨーロッパに興ったと考えられる。
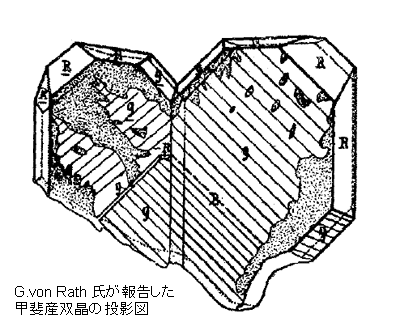
和田博士によると、自身、明治17年にドイツに遊学した折は甲斐産の双晶1ケを携行していったが、多数の標本が市中に出回るようになったのは明治20年代中頃以降だという。倉澤/乙女坂に産したものである。
甲府ではこの頃から水晶を用いた眼鏡のレンズ作りが始まり(No.935)、形状的に数センチ大の平板状結晶が加工に重宝されたという風説がある。
ラート博士のいう心臓形水晶を、日本では俗に夫婦(めおと/みょうと)水晶と呼んだが、この夫婦を別れさせて左右のメガネ玉に磨いたというオハナシで、堀博士の「水晶の本」にも一章が割かれている(「メガネに使われていた水晶の双子」)。面白い話ではあるが、このテの双晶は急速に成長するためか内部に気泡やき裂を含むのが普通で、果たしてメガネ玉に適した質のものが潤沢にあったのか、私としては疑問に思う。
「左右二個がいわばペアーにできているから、メガネ用には都合がよかった」と説かれているけれども、左右で大きさが違っていることが普通にあり(上の図もそう)、当時はすでに甲府に引き割り技術が導入されていたので、通常の大型水晶から質のよい部分を選んで自由に板材を切り出した方が、よほど歩留りに優れ、生産性も上がったはずである。研磨前に必要なメガネ玉の厚みを考えると、そうそう都合よい厚さの平板状結晶が得られたとは考えにくい。そもそも双晶の左右からメガネ玉を1ケずつ取る必然性がない(双晶の接触面はむしろ材料取りの障害になる)。メガネに使うと説いて買い集め、実は海外に標本として流していたのではないか。(補記4、補記5、補記6)
ともあれ明治20-30年代には甲斐産の夫婦水晶は名物となっていて、他の国産標本同様、欧州へ大量に送られたと思しい。パリ万博(明治33年)の際、地質調査所の小川助手は行李一杯の乙女阪産双晶を携行して、現地標本商に卸し、滞在費を捻出した。
1905年(明治38年)、ドイツ・ハイデルベルク大学のフォン・ビクトール・モルデカイ・ゴールドシュミット(1853-1933)は「水晶の双晶様式について」という報文を書いた。彼は双晶の様式を
Ⅰ:双晶の主軸(c軸)が平行なもの、Ⅱ:双晶の主軸(c軸)が傾いているもの とに2大別し、Ⅰ群を回転の有無で2種に、Ⅱ群を双晶面(面指数)の違いで3種に区分した。Ⅱ群の3種は
C: 日本式(C.S.ワイス式)、D: ライヘンシュタイン-グリーゼルンタール式、E:
サルディニア式 で、この日本式がラート博士のハート形双晶に相当する。ゴールドシュミットは、このタイプの双晶標本はほとんどが日本産で、他の産地のものは僅かだから、日本式と呼ぼう、と名称の由来を注釈している。
C.S.ワイスは 1829年にフランス南東部のイゼール県ブール・ドワザンのラ・ガルデットに産した傾軸式双晶を報告したドイツ人である。
ちなみにブラウンズ/スペンサーの「鉱物界」(1912)は、「このタイプの双晶はブール・ドワザン産が久しく知られており、最近では日本から沢山入ってくる」と述べ、図版にラ・ガルデット産と金峰山産とを並べて示している(No.995
に図版紹介)。ラ・ガルデット産は「トの字」形の標本。金峰山産はL字。ザクセンのミュンツィヒやアラスカにも産する、とある。双晶の呼び名には触れていない。秋月博士によると、日本式の名は「ドイツの文献によく用いられたが、英語の論文にはほとんど登場して来なかった」そうだ(「山の結晶」)。
日本では明治時代はたいてい「傾軸式双晶」の名で言及された。和田博士の日本鉱物誌(明治37年/1904年)は、「第三種の双晶(※傾軸式双晶)は我が国においては甲斐、信濃、日向、五島等に産し稀ならざるも、外国においてはその産出稀にして、我が国の産、外人に貴重せらるるものなり」と述べている(補記2)。佐藤博士の「大鉱物学」(大正14年/1925年)は日本式双晶の名を示している。
秋月博士は、「神津俶祐(しゅくすけ)先生やその門下生であった大森啓一先生などが昭和12年頃に、日本双晶を詳しく研究している。この論文は日本語であったため、海外ではあまり知られていなかった。戦後、研究成果を英語でまとめてアメリカの雑誌に発表されたので、日本双晶の名前は鉱物学上で国際的な地位を得ることになった。」(「山の結晶」)と言う。まとめてみると、日本の学界はドイツ人による「日本式双晶」の呼称を歓迎して大正頃から好んで使い始め、戦前この分野の研究を進めて、戦後海外に英語発信したことから世界的に知名となったということだろうか。発案はドイツで、日本が広めた。
ただし、日本よりも早くこのタイプの傾軸双晶が採集されたフランスでは「日本式」と呼ばず、「ラ・ガルデット式」と言うらしい。当然そうあるべきだろう。
cf. 水晶の双晶形式について
日本の産地については、S.神津博士、S.渡邊博士が「水晶の日本式双晶に就いて」(昭和12年/1937年)に、有名なのは二カ所で、第一は甲斐(乙女坂、倉澤、竹森)、第二は五島列島の奈留島と述べ(筆者の一人は明治40年に奈留島産を大量に採集した)、このほか、長野の川端下、宮崎の岩戸村と木浦、石川の阿手鉱山等を挙げている。
ところで近年は大型の国産標本が乏しくなって、たいへんなプレミアがついている。標本市場ではむしろペルー産やマダガスカル産の良品がまだしもまともな値段で流通する。
ペルーでは21世紀に入る少し前、ワンカベリカのパンパ・ブランカ(白原)の町のすぐ近くの2つの小さな鉱区から日本式双晶が出るようになった。町の北方3キロのウルパク山にあったテンタドーラ銅山跡では
1999年から数千点の標本を出した。普通の水晶は20cmサイズ、日本式双晶は10cmサイズに達するものが出て、しばしば共存した。この鉱山は後にフロル・デル・ペルー(ペルーの花)#1と呼称された。
またロザリオ・マーベルという鉱区では 1997年から日本式双晶を出した。量的には少なかったが、無色透明の高品質の標本が見られた。こちらは後にフロル・デル・ペルー#2と称された。画像の標本はテンタドーラ鉱山(フロル・デル・ペルー#1)産。
日本式双晶の形状や成長過程についてはいろいろ書いてみたい疑問点があるが、ページを改める。
一応の気付き点は各画像の直下にそれぞれコメントした。
最後に、ゴールドシュミット博士について。鉱物学の世界でゴールドシュミット(ゴルトシュミット)というと、「現代地球化学の父」と呼ばれる、ビクトール・モーリッツ・ゴールドシュミット(1888-1947)が想起される。オスロ大学、ゲッチンゲン大学で教授を務めた変成岩石学の泰斗で、「鉱物学的相律」、「元素の地球化学的分配則」で知られる。ご丁寧なことに、日本式双晶の名を提唱したビクトール・モルデカイ・ゴールドシュミット(1853-1933)とはイニシャルがそっくり同じで、ぱっと名前を出されてもどっちの人なのか判然しないことが考えられる。もっともモーリッツは
1905年には弱冠17才で学業の途中だった。
益富博士は「鉱物」(1974)に、「この種の双晶を日本式と呼んだのはドイツの、かの有名な岩石学者ゴールドシュミットで、今は世界中で
Japan lawとよばれるようになった」と書かれているが、博士の念頭にはどうもモーリッツがあったように思えてならない。モルデカイはどちらかというと、かの有名な結晶学者である。(補記3)
cf. 日本産の双晶→ No.703(大深山産) No.996(奈留島産) No.995
(ペルー産)
三菱コレクション(旧和田コレクション)中の日本式双晶(乙女鉱山産)→リンク
ヘオミネロ5 (ペルー産の蝶形双晶)
補記:日本式双晶の用語は英語に Japan law twins が正調と思しいが、米国の文献では Japanese twin(s) という表現もよく見かける。神津博士の英語報文でこの語が用いられた影響か。
補記2:和田博士の言う3種とは ドフィーネ式、ブラジル式、傾軸式。前2者は双晶のc軸が平行で、v.V.ゴールドシュミットの言うⅠ群に属する。
ゴールドシュミットのⅡ群E:
サルディニア式を Frondel は高温石英の双晶形態としており(Dana
7th 1962)、低温石英(普通の水晶)ではセラ式 (Sella's law)の名を使っている。
補記3.v.V.ゴールドシュミット(モルデカイ)の
"Atras der Kristallformen"(1913-1923)には総計855の水晶の結晶図が収録されているそうだ。(I.砂川「結晶」(2003))
彼が工夫して作らせた面角測定器(復円反射式ゴニオメータ)は、高精度で使い勝手のよい芸術的なメカである。アンティーク価値抜群。
補記4:余談だが乙女の夫婦水晶は、いいお金になるというので坑夫らがこっそり持ち出して、酒手に代えたものがかなり多量にあったそうである。そしてさらに趣味家の間に流通した。どこで採れたと正直に話すのはマズいので、適当なことを言って濁した。そのため金峯山のあちこちで採れると信じられるようになったという。(しかし、実際あちこちで採れるのも事実のようだ。)
補記5:市川新松博士は、眼鏡のような光学製品を作るには重屈折を生じない晶軸を利用することが大切で、水晶では主軸(※柱軸)に垂直に鏡面を持ってくるのが学理上正しいとし、試しに作らせてみたがこの方向に正確に切れない稚拙な技術の業者が多いと歎じている。
仮に日本式双晶を眼鏡の玉に使うとすれば、柱面を鏡面とすることになるから、当然この学理は守られない。また柱面の(弱い)へき開を利用して材料取りをした場合もやはり要件に従わない。印面を作る時のように柱軸と垂直方向に完全に引き切って漸く条件が満たされるが、精密な光学機器に出来るほどには精度よく切れなかったわけだろう(あるいは柱軸/光軸を意識してレンズに磨く技法がなかったのか)。もっとも水晶の複屈折はさほど顕著ではない。
cf. No.935
補記2 (水晶のへき開方向)
補記6:篠本二郎博士は地質学雑誌に「甲斐金峰山四近の水晶坑」という記事を寄せ(1897)、倉澤産の水晶について次のように書いている。「方言、平板(ひらばん)の夫婦石と云う其の透明無瑕のものは眼鏡を作るに用ゆ、斯学上実に惜しむべきことなれども、多く産出すれば斯学研究材料を得んとするも敢えて乏しきことなし。」
当時はいくらでも手に入ったのだろう。